日本がイノベーション後進国といわれて久しい。しかし近年、21世紀にふさわしいイノベーションを創出すべく、多くの企業で新たな試みが始まっている。それは、「オープンイノベーション」と「デジタル・トランスフォーメーション」だ。イノベーションそのものが“手段の目的化”とならないよう、これらにどう向き合い、マネジメントするかが問われている。みずから先頭に立ち、未来の課題解決のためのイノベーションに取り組む2人に、その要諦を聞いた。
日本のオープンイノベーションは
なぜうまくいかないのか
編集部(以下青文字):イノベーションの創出をめぐりグローバルな競争が激化する中、日本でも、他社との共創によるオープンイノベーションが注目されています。この状況をどうご覧になっていますか。

秋元 比斗志 HITOSHI AKIMOTO
秋元:もともと日本企業は、ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・クリステンセン教授が提唱するような破壊的イノベーションは不得意ですが、過去の成功体験を基礎とする持続的イノベーションは得意です。トヨタ自動車の「カイゼン」などは、その好例の一つといえるでしょう。
しかし、デジタル化によってビジネスモデルが激変し始めたいま、持続的なイノベーションだけでは世界のスピードについていくことはできません。まったく違う次元の変革、破壊的イノベーションが求められています。
多田:ただし、気をつけなければならないのは、イノベーションそのものは目的ではなく、あくまで課題解決のための手段だということです。たとえ最新のデジタルテクノロジーを導入したとしても、それ自体はイノベーションでも何でもありません。それを何のために使うのかという目的がきちんと定義できていなければ、真のイノベーションを成し遂げることはできないのです。
では、そのために必要な要素とは。
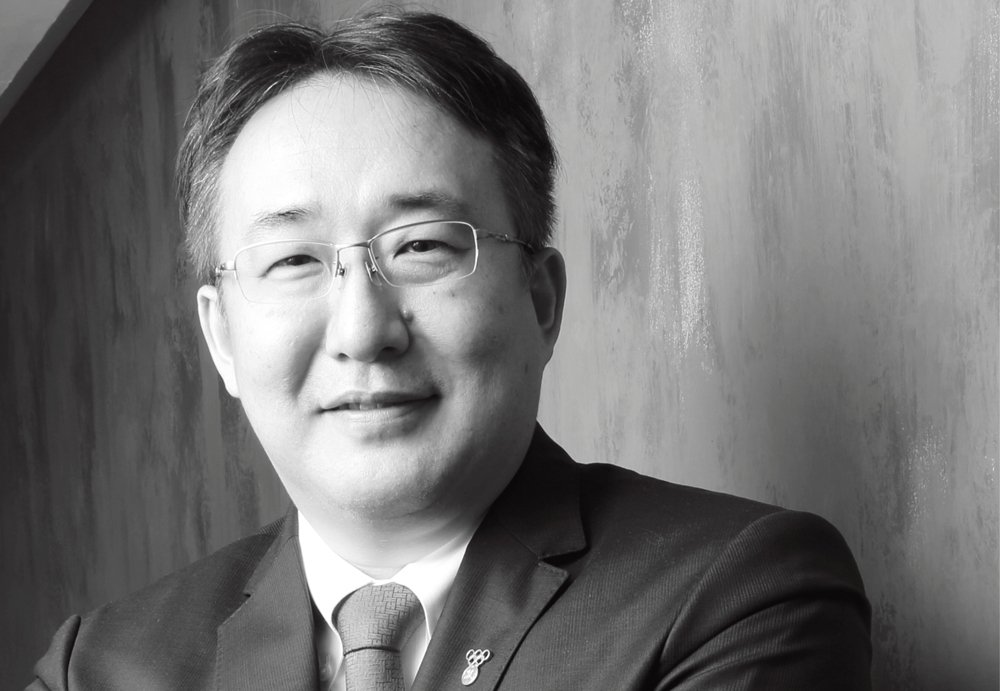
多田:クリステンセン氏は破壊的イノベーターのDNAとして、「関連付ける力」「質問力」「観察力」「ネットワーク力」「実験力」の5つを挙げていますが、私はその中でも、ネットワーク力、つまり外部連携が最も重要だと考えています。
日本の医療における課題は多岐にわたりますが、当社だけで解決できるものは一つもありません。よく、「イノベーションは辺境で起こる」といわれますが、物事を変えるには、違う価値観、軸足、テクノロジーに照らしてみずからを見つめ直す作業が不可欠です。自分たちの常識が外の世界では非常識だと気づかなければ、イノベーションなんて起こせるわけがない。だからこそ、「上手な自己否定」をして、そこから学ぶ力が必要です。その意味で、他社とのオープンイノベーションは、上手な自己否定に有効な場だといえます。
秋元:これまで多くの日本企業は外部連携が苦手で、どうしても自前主義になりがちでした。これは、イノベーション創出において大きな問題です。
私は、イノベーションに失敗する時は、次の3要素があると思っています。(1)網羅的な観点に欠けること、(2)未知の相手とパートナーシップが組めないこと、(3)トップが関与せず、担当者に任せっ切りになりがちなこと。(1)と(2)は明らかに自前主義の弊害です。(3)は経営者自身がイノベーションに対する正しいKPI(重要業績評価指標)を持っておらず、現場任せになっているからだと思います。
多田:当社は外資系企業とはいえ、設立は1982年と日本に根差して長いですし、横河電機との合弁会社でもあるので、生え抜きの社員がたくさんいます。ですので、GEグループ会社のみならず、他業界と学びの場を設定するなど、社内に多様性を醸成するようにしています。日頃から、自己否定できる場に身を置いてカルチャーショックを受けないと、本当の課題は見えてきません。




