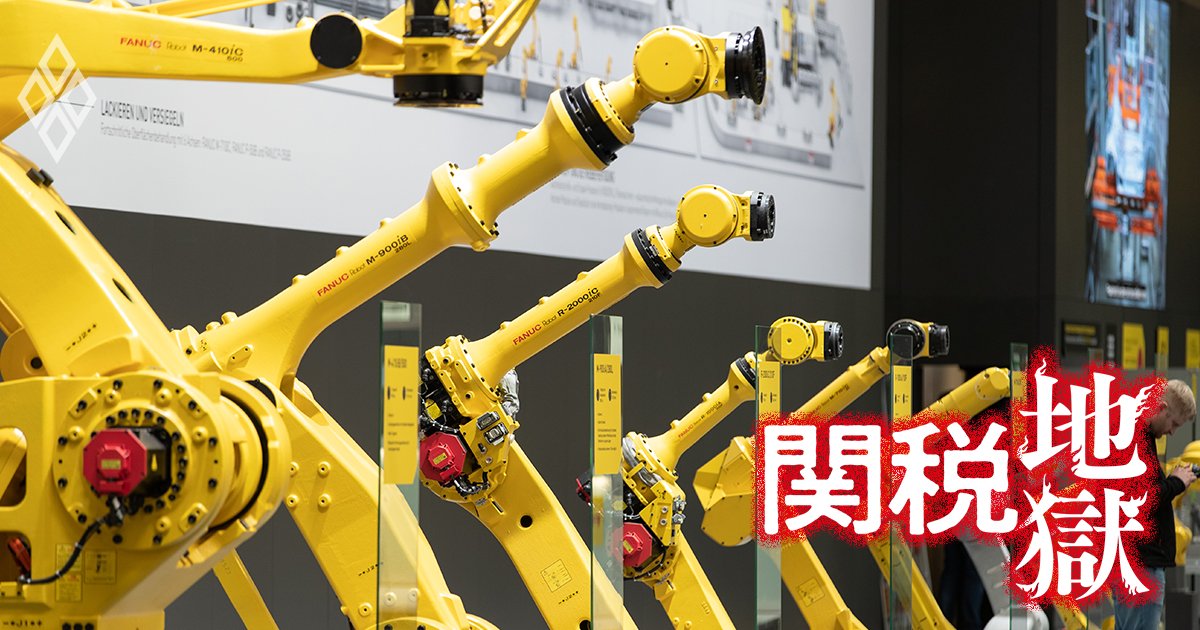練習をじっと見つめる小宮山悟監督 撮影:須藤靖貴
練習をじっと見つめる小宮山悟監督 撮影:須藤靖貴
2019年1月1日、小宮山悟が早稲田野球部監督に就任した。ところが、小宮山・早稲田の船出は「我慢、我慢」の連続だ。「一球入魂」は早稲田の伝統となっており、かつてこの精神がメジャー球団との交流をも可能にした。これに深く共鳴するならば、部の空気は緩むはずはない。小宮山が模索を続ける中、2019年春季リーグ戦が開幕する。(作家 須藤靖貴)
選手の靴下に大きな穴が…
小宮山新監督は日々「我慢、我慢」
暖かく穏やかな新春の朝。2019年1月5日、早稲田大学野球部は西東京市の東伏見稲荷神社に参拝した。
3学年全員が列をなして神門をくぐる。ユニホームの白と鳥居の赤が青空に映えている。新たなチームは前年の秋から練習にいそしんでいるが、監督の正式就任は1月1日。正月休みの明けたこの日が小宮山・早稲田の始動である。白いユニホーム姿の監督を先頭に全選手がお祓(はら)いを受ける。本堂の玄関には選手たちのシューズがずらりと並んでいた。
厳粛な空気の中、監督の目が留まった。
ある上級生の白いソックスの踵(かかと)から肌色が見える。500円玉大の穴が空いていた。
小宮山はゆっくりと息をのみこんだ。
もし自分が学生時代に同じことをしたら――。
石井連藏監督からどんな痛棒を食らわされただろうか。いや、服装の不備などは論外だ。しょっぱなからこんな大穴をさらすことなどあり得ない。所作を整え、立ち居に注意を払ってもなお、思いがけないことで叱咤(しった)を浴びることもあったのである。
だが、小宮山は呆気(あっけ)を表に出すことはなかった。
「我慢、我慢」
これが新監督の口癖である。
「早稲田大学野球部を正しい姿に戻す」を
掲げた小宮山新監督の苦労
4月開幕の東京六大学春季リーグ戦に向けて、早稲田大野球部の戦力は申し分ないものだった。投手陣は当時3年生の早川隆久を軸に身長2メートル左腕の今西拓弥、柴田迅、2年生の徳山壮磨、西垣雅矢と充実。彼らの球を受ける4年生捕手・小藤翼の安定感も頼もしい。打線もキャプテン加藤雅樹、檜村篤史、福岡高輝のクリーンアップトリオが最終学年を迎える。ライバル慶応大など他校と比較しても十分に優勝が狙えると目され、小宮山もその通りだと思った。
しかし、どこか物足りない。