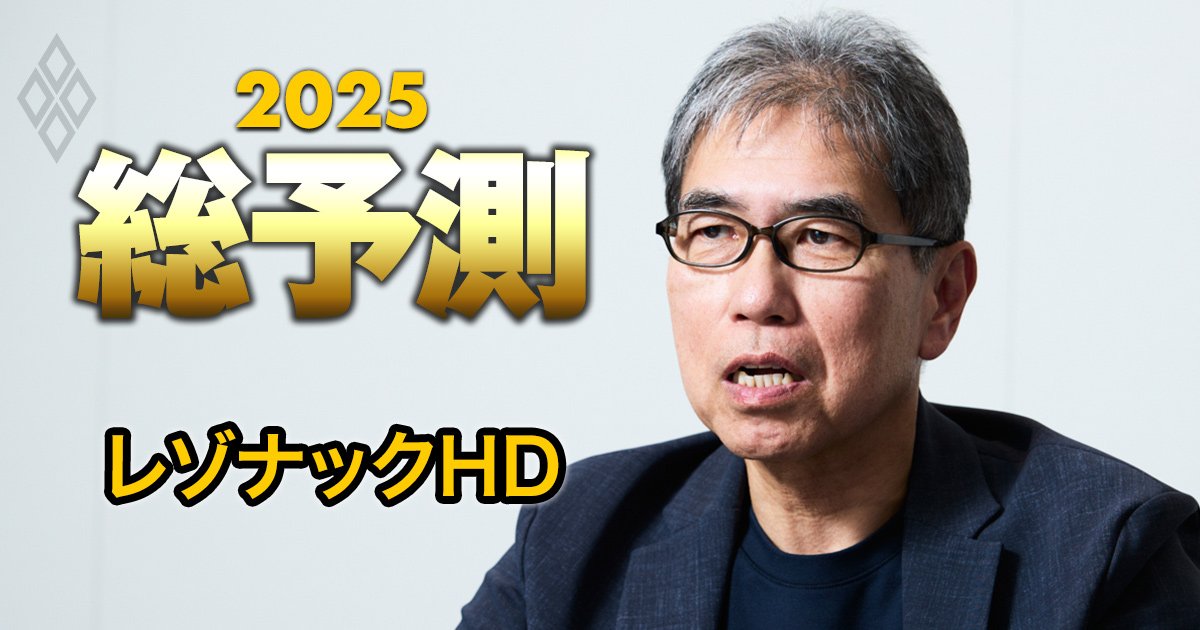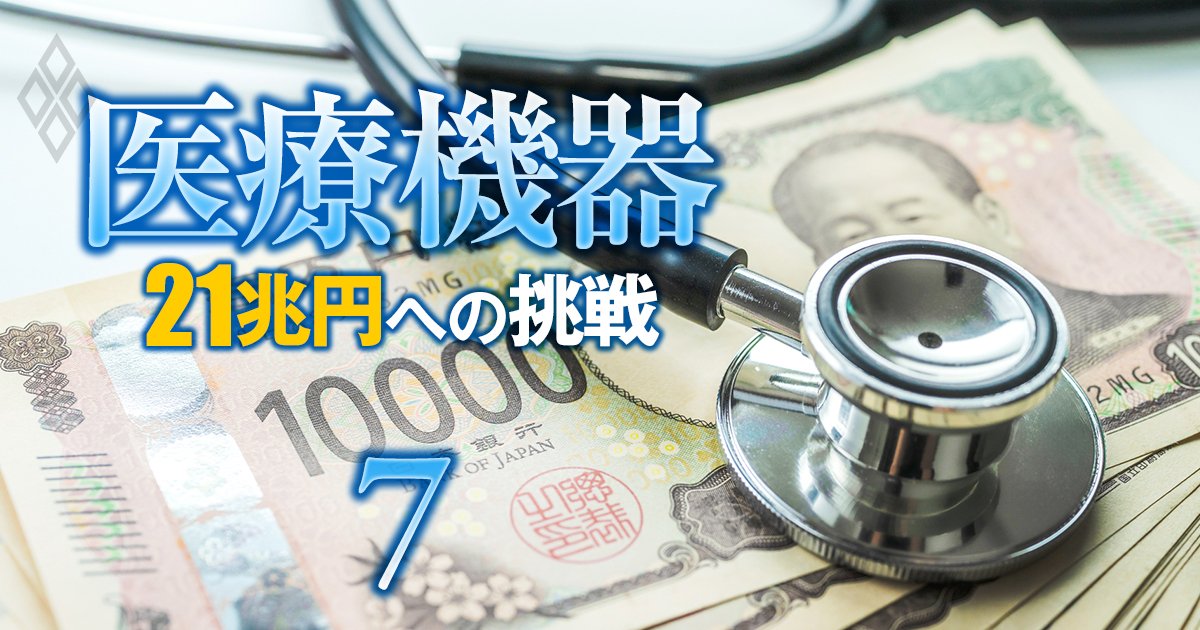写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
梅雨が始まると、急な気圧や気温の変化によって、体調を崩す人が少なくない。その症状は、頭痛やめまい、倦怠(けんたい)感などさまざま。このような不調は「気象病」とも呼ばれ、近年、認知が広がりつつある。そんな中、気圧の変化を知ることで体調管理に役立てるアプリが重宝されている。天気予報を見るように、事前に起こりうる体調不良を確認できることから、利用者が増えているという。
* * *
「曇りや雨の日は、眠気や頭がモヤモヤするような頭痛に襲われることがあります。でも、病院に行くほどでもなかったんです。最近になって、それが気圧に左右されているとわかり、少し気持ちが楽になりました」
こう話すのは、片頭痛持ちの30代女性。夫も同じタイミングで頭痛を訴えていた。「気象病」というのがあることを知り、自分たちの不調が気圧の影響を受けているかもしれないと思ったという。
気圧などの変化で不調をきたし、病院を訪れる人は少なくない。