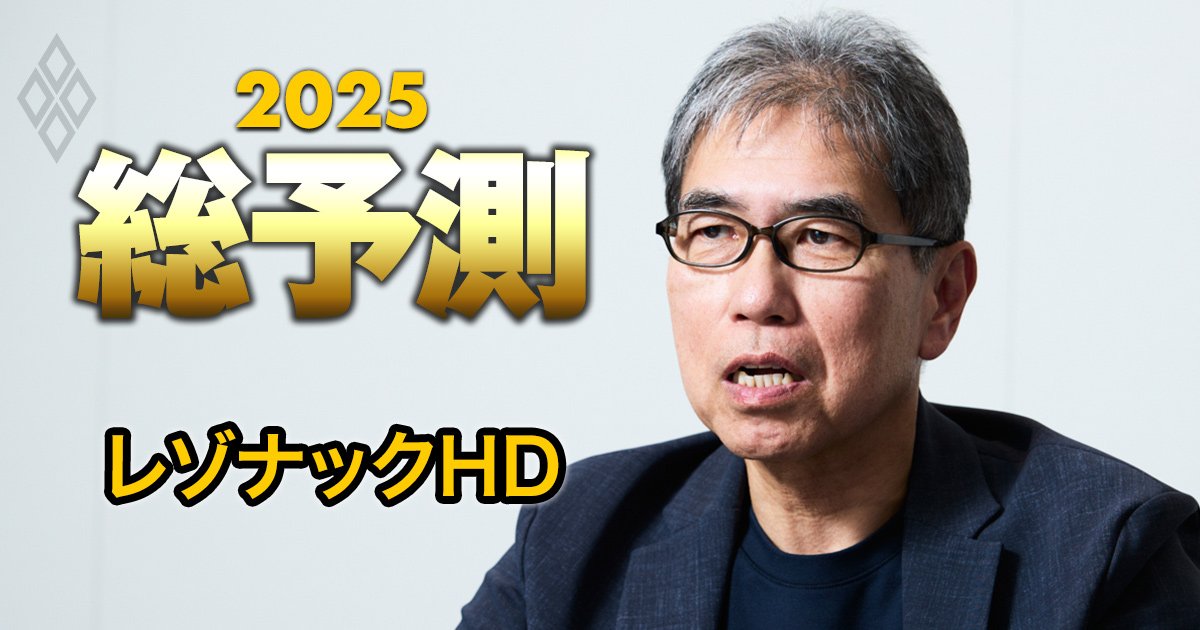思考OSをアップデートしていけば、思考や生き方の選択肢が増えていく(写真はイメージです) Photo:PIXTA
思考OSをアップデートしていけば、思考や生き方の選択肢が増えていく(写真はイメージです) Photo:PIXTA
おすすめポイント
私たちは幼い頃から長い時間をかけてたくさんの勉強をしてきた。はたしてそこで得た知識をどれだけ上手く活用できているだろうか。歴史上の出来事の名称や年号を暗記しても、それがどのような意味を持つのか、私たちがどのような教訓を得られるのかを深く考えなければ、本当の意味で学びを得たとはいえない。
 『視点という教養 世界の見方が変わる7つの対話』 深井龍之介、野村高文著 イースト・プレス刊 1760円(税込)
『視点という教養 世界の見方が変わる7つの対話』 深井龍之介、野村高文著 イースト・プレス刊 1760円(税込)
本書『視点という教養 世界の見方が変わる7つの対話』は2021 JAPAN PODCAST AWARDSベストナレッジ賞番組「a scope」を書籍化した一冊だ。著者の二人が様々な分野の専門家と対談して、学びを得ていく。文化人類学、物理学、仏教学、脳科学。こういった各界の専門家たちとの対談に、読者は知的好奇心を大いにかきたてられるだろう。印象的なのは、著者らが各分野を掘り下げていくだけでなく、他の分野とのつながりや共通項を見つけていくプロセスからも学びを得られる点だ。
そもそもリベラルアーツとは、古代の「自由人」が備えるべき教養を意味する。伝統的に文法学、修辞学、論理学、数学、幾何学、天文学、音楽の七科目と定められているが、本書はその枠組にこだわらない。時代が変われば求められる教養も変わるからだろう。また、様々な学問分野に関する知識量よりも、そこからどんな視点が得られるかが重要となる。
本書を通じて思考OSをアップデートしていけば、思考や生き方の選択肢が増えていくことだろう。世界を見る目が変わること請け合いの一冊だ。(大賀祐樹)