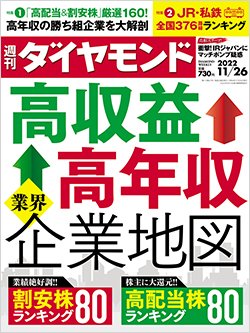20年間で上昇した日本の年収は3.3%
韓国やニュージーランドにも追い抜かれた
残念ながら、日本の給与の低空飛行ぶりは、データを見ると一目瞭然だ(下図参照)。
OECD(経済協力開発機構)の統計によれば、2021年の日本の年収水準(購買力平価実質ベース)は、比較可能な加盟34カ国で下から11番目(図は主要国のデータを抜粋して表示)。世界トップの米国の半分強にすぎない。
過去からの年収増減率を見ると、日本は20年前(01年)比で3.3%増、10年前(11年)比では1.7%増。いずれも34カ国中、下から数えて6番目という停滞ぶりだ。
要するに、名目と実質の違いがあるとはいえ、数字だけ見れば足元では1年前と比べ4%近く物価が上昇中なのに、年収が20年間で3%強しか上がってこなかったのだ。そして、日本の年収水準はこの間、国内総生産(GDP)の規模では大きく勝る韓国やニュージーランドにも、次々と追い抜かれてきた。日本はGDPでこそ、「世界3位の経済大国」の体裁を保っているものの、給与に関しては、決して「先進国」とはいえない実情が浮かび上がるのだ。
国内市場縮小、経営環境悪化、先行き不透明感……。企業が「賃上げできない理由」を並べ立てるのは簡単だ。史上最高益を稼ぎ出していながら、ベアはおろか、ボーナス増額に渋い顔をする企業も数多い。人件費の増加が財務上、収益圧迫要因となるのも事実だ。
しかし、根強い年功序列型の閉塞感や、やりがい搾取的な環境に嫌気が差し、将来を嘱望されていたはずの若手層などが大手企業からも相次ぎ離職している。ある転職支援会社のトップは、「大企業の経営者も、給与を上げないから人が辞めているという現実と真摯に向き合うべきだ」と訴える。
表向きは「実力主義」や「若手重用」「人財こそ重要」などとうたうものの、痛みを伴う大胆な待遇改善は一向に行わない──。未来ある優秀な人材なら、そんなじり貧マインドにむしばまれた組織には愛想を尽かし、より良いキャリアを求めるのは合理的な選択だ。
実は、日本にも平均年収が優に1000万円を超えるような高年収企業も確実に存在する。最新版の平均年収ランキング上位20社を示したのが下表だ(本特集で解説する企業は、表の右に特集号の該当ページを記載した)。
M&Aキャピタルパートナーズ2688万円、キーエンス2183万円、ヒューリック1803万円……。こうした勝ち組企業の多くは、高収益を給与アップにつなげ、さらに優秀な人材を呼び込む好循環を実現している。
また投資家の視点で見ても、人材にきちんとお金を出す企業には、今後の成長が期待できる。
何しろ近年は、企業の評価軸として、「人的資本」の存在が注目されている。企業の収益を生み出す従業員の価値や、従業員の知識・技能のことを指す言葉だが、給与(年収)はその最たる尺度ともいえる存在だからだ。
実際、「平均年収が高い企業は株式パフォーマンスも良い」ことをデータも実証している。
以下はその概略だ。ニッセイアセットマネジメントの吉野貴晶投資工学開発センター長の比較調査では、まず、東証株価指数(TOPIX)構成銘柄の3月期決算企業のうち、平均年収上位3分の1を「年収が高い」一群、下位3分の1を「年収が低い」一群とした。
分析の期間は10~19年度の10年、株式パフォーマンスは各年度3年間で計測。すると、最新の19年度のパフォーマンス格差は27.1%となった。つまり、平均年収が高い企業の方が、低い企業より、株式投資収益率で大幅に上回る結果を示したのだ。