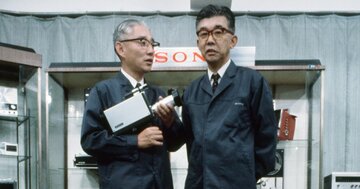悪口は必ず
優劣関係が表明する
最後の劣位化説は、人々の心中ばかりに注目するのではなく、人々の立場やランク(位)に焦点を当てる考えです。劣位化説の基本的な発想は、悪口を言う人は、自分の優位性を確認したり証明したりするために、いわば「マウントを取る」ために、悪口を言うというものです。そして、悪口が悪いのは、人間同士にランクの上下や優劣関係を作ることが良くないからです。
劣位化説によると、悪口は必ず人物同士の比較と優劣関係の表明を必要とします。誰かを誰かと比べて、その人物がより劣っている、ランクが下であると表すことが悪口の中心的部分で、人が傷つくかどうか、悪意があるかどうかは、悪口のあくまで周辺的な要素になります。
例えば、誰かを「きもい」と直接的悪口を言うことは、その人物を否定的に評価し、自分よりも劣っている、自分よりも下である、と述べているわけです。「きもい」のような否定的語句を含まない間接的な表現でも、単なる違い・差異を記述しているのではなく、それで優劣関係を表しているのが明らかならば、悪口と解釈されるでしょう。
またランクの上下関係は権力関係の上下を意味しますので、悪口は権力差を表明します。「きもい」といったラベルを使う、嫌なあだ名で呼ぶ、「あっちいけ」といった命令をする、そういった典型的な悪口は、その内容とは無関係に、「私にはこんなことが言える・できる力がある」というメッセージを発しています。例えば、人の呼び方を決められるというのは一種の権力です。悪口はそれを誇示することにより、誰かを劣位に置くわけです。
 『世界最先端の研究が教える すごい哲学』(総合法令出版)
『世界最先端の研究が教える すごい哲学』(総合法令出版)稲岡大志 編, 森功次 編, 長門裕介 編, 朱喜哲 編
個人間には実際のところ、身体的特徴や能力の差異があります。しかしそうした事実上の違いが、上下・優劣・支配関係を生じさせるべきではない、というのが現代社会の理念です。身分社会はもう終わったはずなのです。ですので、ランキングの上下を作ってしまう悪口は、人を傷つけなくても、悪意がなくても悪い、ということになるわけです。
劣位化説は悪口にまつわるいろいろな現象を説明することができます。その一つは、いわゆる自虐が他人への悪口より許容されることの説明です。自分は自分であり、自分が自分よりランクが上とか下とかはナンセンスです。そのため、自分に対して自虐的に悪口を言っても、悪口を言っている側(自分)がターゲット(自分)より優位に立つことはありません。
他にも、劣化説を踏まえると、悪口のようだが状況次第で悪口でなくなる事例や、一見悪口ではないが状況次第で悪口となる事例がありますので、皆さんも考えてみてください。