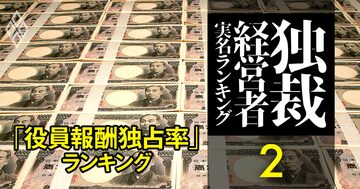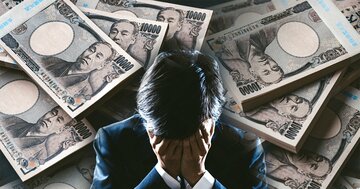日本企業の預貯金は、世界一の経済大国であるアメリカ企業の2.5倍にも及ぶのだ。
また株主に対する配当も、この20年で激増し、2倍を大きく超えている。つまり、株主配当も役員報酬も激増し、会社には巨額の預貯金が貯め込まれている。それにもかかわらず、社員の賃金だけは下げ続けられたのだ。
これでは、日本経済が停滞して当たり前である。
企業が人件費を切り詰めれば、一時的に業績は好転する。しかしブーメランとして、やがて業績の悪化につながっていく。
繰り返しになるが、企業が人件費を切り詰めれば、国民の収入は下がり、購買力も低下する。国民の購買力が低下するということは、企業にとっては、「市場が小さくなる」ということである。市場が小さくなっていけば、企業は存続できなくなる。
それは、当たり前と言えば当たり前であろう。
前述したように、2002年には一世帯あたりの家計消費は320万円をこえていたが、2022年は290万円ちょっとしかない。その結果、企業収益はいいのに、国内消費(国内需要)は減り続けることになる。
国内消費が減り続けていることは、GDPを押し下げる要因ともなる。企業の国内売り上げが減ることはGDPの低下に直結するし、賃金の低下もGDPの低下に直結するのだ。
国民1人あたりのGDPにおいて、日本は大きくランクを下げていることは前述したが、その主要因の一つが人件費削減なのである。
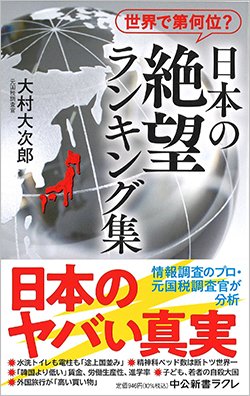 『世界で第何位?日本の絶望ランキング集』(中央公論新社)
『世界で第何位?日本の絶望ランキング集』(中央公論新社)大村大次郎 著
賃金というのは、日本経済の活力源なのである。これを増やさなければ、日本経済はどんどん元気がなくなっていく。
昨今、日本の政財界も、ようやくそのことに気づいて最近では賃上げを推進しようとしている。しかし、バブル崩壊後から続いている、先進諸国との賃金格差を埋めるにはまだ全然足りないと言える。
人件費を30年前の倍くらいに上げないと、日本経済が本当に復活することはないと言えるだろう。日本企業は莫大な内部留保金を抱えており、そのくらいの経営体力は十分にある。このままでは日本は、巨額の財宝を抱えたまま沈没する船となってしまうのだ。