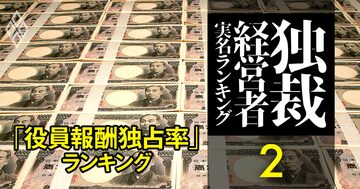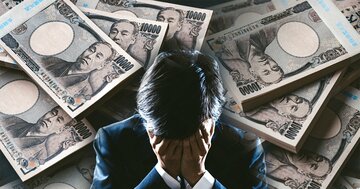2010年3月期決算から上場企業は1億円以上の役員報酬をもらった役員の情報を有価証券報告書に記載することが義務付けられたが、2010年の上場企業では364人もの1億円プレーヤーがいたことが判明し、世間を驚かせた。が、上場企業の1億円プレーヤーはその後も激増を続け、2021年には926人になっているのだ。
企業によっては、社員の平均給与の200倍の報酬をもらっている役員もいた。
以前はこうではなかった。
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われ、日本企業が世界経済で最も存在感が大きかった1980年代、役員報酬はその社員の平均給与の10倍もないところがほとんどだった。
欧米の役員や経済学者たちは、そのことを不思議がったものである。
「従業員の給料はしっかり上昇させ、役員報酬との差は少ない」
「会社のトップがそれほど多くない報酬で最高のパフォーマンスをする」
それが80年代までの日本企業の強さの秘訣だったのだ。
しかし、いまでは役員と従業員の報酬は、欧米並みか、それ以上の差がある。そして、従業員の賃金は、欧米では考えられないようなペースで、下げ続けられてきた。また欧米では絶対ありえないような陰湿な方法で、リストラが敢行されてきた。
GDPを押し下げる
低賃金政策
バブル崩壊以降、日本企業が従業員の賃金を下げ続けてきた理由は、必ずしも経営が苦しいためではない。
日本企業は、バブル崩壊以降に内部留保金を倍増させ2021年には500兆円にも達している。また、保有している手元資金(現金預金など)も200兆円近くある。
これは、経済規模から見れば断トツの世界一であり、これほど企業がお金を貯め込んでいる国はほかにない。アメリカの手元資金は日本の1.5倍あるが、アメリカの経済規模は日本の4倍以上であることをふまえれば、日本の企業はアメリカ企業の2.5倍の手元資金を持っていることになる。