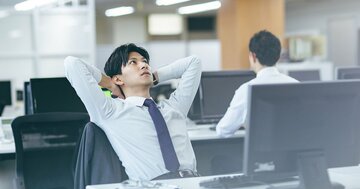時代や宗派で変わる「功徳」の意味
意識せずに他者のために行動を
 同書より転載
同書より転載
「功徳」は梵語グナの漢訳です。「功能福徳(くのうふくとく)」という意味で、よい行為(善を積んだり仏教修行をすること)の結果として、報いとして得られる果報のことを言います。「功徳」の「功」は幸福と利益の功(はたら)き、「徳」は「得」です。
仏教ではもともと功徳は自分ではなく他者のために、見返りを求めずに善行を積めばよい果報が得られるよ…とされてきましたが、それが「良いことをするとご利益が得られる」と拡大解釈されて、今では世俗的な意味が強くなっているようです。
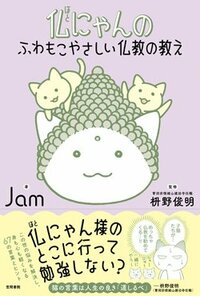 『仏にゃんのふわもこやさしい仏教の教え』(笠間書院)
『仏にゃんのふわもこやさしい仏教の教え』(笠間書院)Jam 著、枡野俊明 監修
どんな行為が功徳であるかは時代や宗派により異なります。平安時代では経典を読んだり写経をしたり、祈祷をしたり、お布施をすることが功徳であると考えられていました。
「南無阿弥陀仏」を唱えることが最高の功徳だという宗派もあります。今の時代の日常において功徳について考えるなら、「ご利益などの見返りを求めず他者のために善い行いをする」ことでしょうか。
「無功徳」という禅語があるのですが、これは、「善を行っても功徳がない、善の行為は無心のもので果報を当てにしてはならない」という意味です。
「今、自分は善いことをしているな」と意識せずに他者のために行動するのは難しいことかもしれませんが、自然とそうなれたら素敵ですよね。