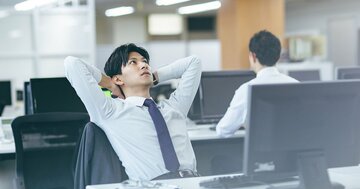「我慢」は仏教語で煩悩を表す?
我を張るのをやめて気楽になろう
 同書より転載
同書より転載
今は耐え忍ぶ意味などで使われていますが、「我慢」とは、もとは高慢なことや我を張ること、我執など、自分の意見に固執することを言います。
本来は仏教語で、「自分をえらいと思い込み、他を軽んじて心おごること、慢心すること」で煩悩の一つです。
ところで、一般的な煩悩にはもととなる煩悩があり、それを「根本煩悩」と言います。根本煩悩には「我癡」「我見」「我慢」「我愛」の四種類があるとされ、それを四根本煩悩(しこんぽんぼんのう)と言います。
「我癡」は一切の煩悩の根本で、愚かさ、無明(無知や真理に暗いこと)です。「我見」は、いつも自分が中心であり主体であると思い込んでしまうこと。「我慢」は、思い上がりの心、うぬぼれの心、おごり高ぶること。「我愛」は、無意識に自分を愛することです。
我慢者(うぬぼれて我意を通す自分勝手なわがままな者)という言葉などは、まさにその意味で使われています。「徹底的に耐えて我を張る」ところからという説もあります。
我慢はつらいですよね。でも、もとの意味も知ると「我慢ばかりしなくてもいいかな?」と思えませんか?
一人で耐え忍んで「周りに頼れない、一人でなんとかせねば」と思うのは、「周りには頼らない、一人でなんとかできる」という慢心かもしれません。耐えることで我を張るのをやめたら、少し気楽になれそうです。