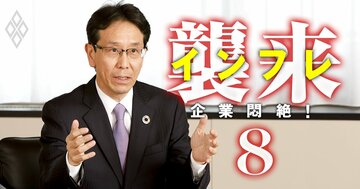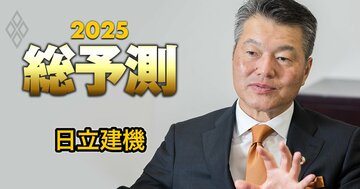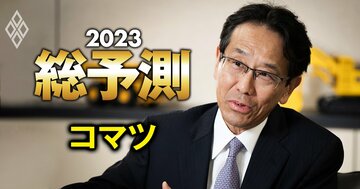Photo:Matt Cardy/gettyimages
Photo:Matt Cardy/gettyimages
コマツと日立建機の2023年度の営業利益の各6割は部品の供給とアフターサービスが稼ぎ出している。建機のメンテナンス支援で利益を生む業態は、世界各地に代理店網を築いた日系の建機メーカーや総合商社の強みを生かすことができ、多大な利益もたらしてきた。このシステムをさらに改良できるかどうかが、激化する中国メーカーなどとのシェア争奪戦での勝敗を分ける。特集『建機 陥落危機 メーカー&商社“背水の陣”』#6では、メーカーと商社が構築してきたスキームと今後の課題をつまびらかにする。(ダイヤモンド編集部 井口慎太郎)
地球と闘う機械、消耗は当然
部品・サービスの営業利益率は30%超!
設備投資の最初に導入される建機は、時代の景況感を敏感に反映する。需要の変動こそ激しいものの、市場は成熟しており、勢力図やプレーヤーが目まぐるしく変化することはない。端的に言えば派手さとは程遠い堅実な業界だ。
コマツは2023年度に連結売上高で過去最高を更新。総合商社も一部の代理店に長年出資して流通を下支えし、着実に利益を上げている。つまり、地味さと裏腹に「うまみ」のにおいがそこはかとなく漂っている。そのうまみの正体は長期的なアフターサービスで稼ぐ独特の販売システムだ。
コマツと日立建機の23年度の営業利益に占める部品・サービスの割合は、各6割に上る。日立建機の関係者によると、同年度の同社全体の調整後営業利益率は12%だが、部品・サービスに限れば30%を超えるという。メーカーの稼ぎどころは新車販売ではなく、部品とアフターサービスなのだ。
「地球と組み合って、闘う機械」。建機メーカー幹部がそう口にするように、建機は岩盤やコンクリートの掘削など過酷な環境で使用される。最も台数が多い油圧ショベルの耐用年数はおおむね8年だが、その間にバケットやエンジン、油圧ポンプなどさまざまな部品を消耗し、交換することになる。
近年売り上げを伸ばしている鉱山機械ではさらに保守サービスの重要性は増す。資源採掘の現場で稼働する超大型のダンプトラックや油圧ショベルは24時間365日稼働することもある上、耐用年数も10~15年と長い。その途中でのオーバーホールは欠かせない。
ユーザーが最も困るのは作業現場で機械が止まることだ。その最悪の事態を回避するためにICT(情報通信技術)が役立っている。コマツは01年に「Komtrax」を標準搭載した建機を導入。日立建機は13年に「ConSite」を取り入れた。建機を遠隔で監視し、稼働状況や燃料消費量、部品の消耗具合を読み取り、修繕が必要な時期に営業をかけられるようになっているのだ。
ICTの普及により、適切なタイミングでメンテナンスすることにより結果的に建機の稼働率が上がる認識がユーザー間に浸透していった。
次ページでは、コマツと日立建機の新車販売とアフターサービスの売上高の割合の変化と今後の課題を明らかにする。