井口慎太郎
#28
トヨタ自動車などのトヨタ自動車グループによる豊田自動織機への株式公開買い付け(TOB)が佳境を迎えている。トヨタ自動車グループは1月中旬にTOB価格を引き上げたが、アクティビスト(物言う株主)の米エリオット・インベストメント・マネジメントなどがTOB価格は不十分として徹底抗戦の姿勢を見せている。ところが、エリオットをはじめとする複数のファンドが、昨年のTOB観測報道後の株価急騰時に豊田自動織機株を大量に取得していたことがダイヤモンド編集部の取材で判明した。「さや抜き」狙いとみられる主要ファンドの顔触れに加え、その“巧妙な手口”を明らかにする。

豊田自動織機と三菱ロジスネクストというフォークリフト大手2社への株式公開買い付け(TOB)が、それぞれ同時に実施されている。トヨタ自動車と三菱重工業という“盟主”の意向が強く働いているとみられる二つのTOBは、少数株主からどう見られているのか。TOBのプロセスの妥当性や透明性から検証する。

2026年1月から住友重機械工業の社長に就任する渡部敏朗・最高財務責任者(CFO)は、同社のトップとしては珍しく財務畑を歩んできた。異例の抜てきの背景には、業績が伸び悩み、株式市場からの評価も上がらない現状を打開しようとする意図がある。渡部氏に「痛みを伴うこともやむなし」とする構造改革の決意を聞いた。

#9
半導体・電子部品業界は、人工知能(AI)普及の追い風を受けているが、全体が右肩上がりというわけではない。電気自動車(EV)シフトの鈍化や部品のコモディティー化、激しい国際競争でかつての有力銘柄も逆風にさらされているのだ。今回は、半導体・電子部品業界の倒産危険度を検証。“危険水域”にランクインした18社の顔触れを明らかにする。

産業用ロボットや工作機械に用いるサーボモーターの世界大手、安川電機は自動車産業や半導体産業の設備投資の最新情勢を知る立場にある。米国の関税政策は2026年の設備投資にどんな影響をもたらすのか。さらに、同社は「フィジカルAI」分野で米エヌビディアと富士通と協業する。人型ロボット開発ブームが再燃する中で、安川電機の本気度は?小川昌寛社長に展望を聞いた。

にわかにバズワードとなった「フィジカルAI」。生成AIの普及が目覚ましかっただけに期待感は高まっている。日系の製造業や通信事業者も巨大市場へ打って出ようと協業関係を盛んに結んでいる。フィジカルAIに商機を見出している各社の動向からは、手指の動きがカギになることがうかがえる。巨額投資を続ける米中勢に対抗する、日系企業の勝ち筋を探る。

日本、イギリス、イタリアの3カ国で共同開発している次期戦闘機の最重要機器とされる「ミッションコンピューター」を、イタリアの防衛装備品メーカーのレオナルドが担う方向で調整が進んでいることが、ダイヤモンド編集部の取材で判明した。三菱電機も同機器の開発で主導的な立ち位置を目指していたが、及ばなかったもようだ。日本の需要に沿った形で次期戦闘機を運用できるかどうかが今後の焦点となる。

日立建機は2027年4月に社名を「ランドクロス」に変更する。既に日立製作所の持ち分法適用会社ではなくなっている。米国の関税政策の影響が本格化する中、26年は、いかに中国の建機メーカーなどとの競争に勝ち抜くのか。先崎正文社長に、日立ブランドから“独り立ち”した後の展望を聞いた。
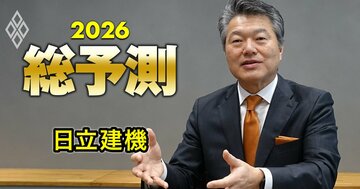
#8
不適切会計疑惑に揺れるニデックは、減損損失の計上を恣意的に先送りし、利益を多く見せていたのではないかと指摘されている。監査法人が独立性を保てていたのかどうかも焦点となっている。会計と企業ガバナンスを専門とする八田進二・青山学院大名誉教授にニデックの問題点を聞いた。

造船業が一躍脚光を浴びている。日米合意に基づく対米80兆円投資に日米の造船所の能力強化が含まれ、日本政府の重点投資分野にも造船が指定された。10年間で日本国内の建造量を倍増させるため、官民による“1兆円基金”も動き出した。本稿では、日本の造船業が規模で勝る中国・韓国勢に対抗する勝ち筋を詳述する。日米合意に基づく巨額投資は、日本の造船業の停滞を打破するカンフル剤になるのか。

#11
機械業界の日系メーカーは、伝統的に高い技術力を持ち、海外でも優位性を発揮してきた企業が多い。しかし、足元では原材料費の高騰や海外の競合の台頭で競争力が衰えている会社も少なくない。今回は、機械業界の倒産危険度を検証。“危険水域”にランクインした27社の顔触れを明らかにする。

2026年1月から住友重機械工業の社長に就任する渡部敏朗・最高財務責任者(CFO)は、同社のトップとしては珍しく財務畑を歩んできた。異例の抜てきの背景には、業績が伸び悩み、株式市場からの評価も上がらない現状を打開しようとする意図がある。渡部氏に「痛みを伴うこともやむなし」とする構造改革の決意を聞いた。

#9
半導体・電子部品業界は、人工知能(AI)普及の追い風を受けているが、全体が右肩上がりというわけではない。電気自動車(EV)シフトの鈍化や部品のコモディティー化、激しい国際競争でかつての有力銘柄も逆風にさらされているのだ。今回は、半導体・電子部品業界の倒産危険度を検証。“危険水域”にランクインした18社の顔触れを明らかにする。

#3
マツダが行ったシニア世代の希望退職は、途中で方針が変わって500人で打ち切られた。先着順を争う“クリック競争”による椅子取りゲームはなぜ起きたのか。そして、退職できた人とできなかった人の運命の分かれ目はどこにあったのか。担当記者が動画で解説する。

#1
希望退職者を募集しているマツダが、突如として募集人数に上限を設けたことがダイヤモンド編集部の取材で分かった。先着順で決める残り90人の枠に入れなければ、最大で4000万円に上るとみられる割増退職金は受け取れず、ただの自己都合退職になってしまうというのだ。本稿では、関税地獄のただ中にあるマツダの本音と建前を関係者への取材で明らかにするとともに、リストラを迫っている根本的な経営課題にも迫る。

#9
防衛費増額の追い風を受けて、かつてない好業績を収めている三菱重工業、川崎重工業、IHIの3重工。今は構造改革を進めるまたとない好機ともいえる。そこで注目されるのがトップ人事だ。3社では歴代、どのようなキャリアを歩んだ幹部がトップに上り詰めているのか。本稿では、関係者への取材で3社の次期社長候補の実名を明らかにする。

#5
IHIは営業利益の8割以上を航空・宇宙・防衛部門が稼ぎ出しており、三菱重工業と川崎重工業に比べてもエース事業がはっきりしている。ただ、航空エンジンは品質問題の発生リスクや、事業環境の変動が大きいため、“第2の柱”が求められて久しい。本稿ではIHIの井手博社長に、さらなる事業再編の方向性や、現在の好況の真因を聞いた。
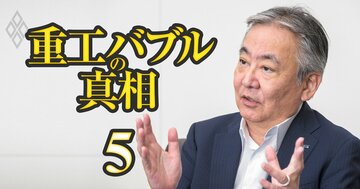
#2
マツダが、希望退職者の募集を12月1日に打ち切った。当初は想定した500人を超えても受け入れるとしていたが、急きょ、定員ちょうどで打ち切ると方針転換し、残る90人の枠を巡って申請の「椅子取りゲーム」が繰り広げられた。本稿では、早期退職を希望するベテラン社員が殺到し、1分足らずで受け付け終了となったマツダの「決戦の日」の模様とともに、会社側が、シニアの人生プランを左右する希望退職の重大な“運用変更”についてどう考えているかをお伝えする。

#4
三菱重工業、川崎重工業、IHIの重工3社は幅広い事業を手掛けている。裏を返せば、稼ぎの悪い“お荷物事業”を切り捨てずに持ち続けてきたのだ。それが近年では、稼ぎの良い事業とシナジーがなければ見切りをつける冷徹な姿勢を見せるようになってきている。企業価値が上がり、さらなる成長への期待感も高まる中で、構造改革の必要性も増している。一歩先に行く会社と、遅々として改革が進まない会社はどこか。本稿で明らかにする。

#23
実は日本の上場企業には「年収1億円以上」のビジネスパーソンが1199人もいる。果たして、どんな顔触れなのだろうか?報酬が、諸外国に比べて低過ぎるという指摘もあるだけに、年収が高いこと自体は批判されるべきではないだろう。ただ、業績や株式市場からの評価が振るわないにもかかわらず、1億円ももらっているのであれば、従業員や株主は心穏やかではいられないかもしれない。今回は、機械業界の役員報酬ランキングを公開する。
