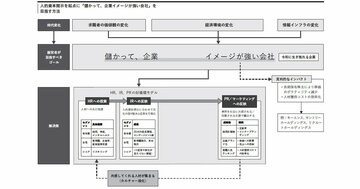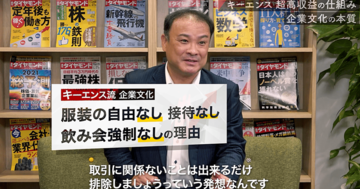本当のニーズを掴むには
顧客の見ている先を見る
顧客自身が自身の本質的なニーズをしっかりと把握していれば、単純にそれを実現すればいいので難度はそれほど高くありません。ところが、今回の「人手が足りなくて困っているのでロボットなどを活用して自動化を進めたい」というような、ニーズが漠然とした依頼では、まず「何がどう問題なのか」を捉える必要があります。
依頼者に詳しく聞いてみた結果、「配膳の人手が足りないので配膳を自動化したい」というニーズが出てきたとします。最初のものよりは具体的になったため、一見、顧客ニーズをしっかりと拾えています。しかし注意しないといけないのは、顧客の要望には「顧客の主観や作文」が含まれている点です。額面通りに受け止めるべきではありません。
顧客は、自分が見える範囲(普段接している業務など)の問題点は良く見える(気づく)一方で、他の業務や、問題そのものの本質には気付かないケースが多い。先ほどの「配膳の人手が足りない」という問題について「なぜ配膳の人手が足りないのか」という「問題の本質」が抜けてしまいがちなのです。
もしかしたら、配膳の人手が足りない理由は、調理の優先順位付けにあるかもしれません。同じようなオーダーが入る可能性があるにもかかわらず、1つひとつの注文に対して1人前ずつ作って配膳し、配膳の効率を落としている可能性があります。このケースだと、配膳の自動化をする前に、オーダーから調理に至る作業の効率化が、配膳の人手不足問題の解決にとっても有効です。
このような視点で見ると、「配膳の人手が足りないので配膳を自動化したい」というニーズに対して「配膳作業にロボットなどを入れて自動化する」というのは、表面的なニーズを拾っているだけです。仮に導入に至っても、問題の本質がオーダー周りにあるならば、人手不足を根本的に解決できない可能性が残ります。つまり、これだと顧客にとって役立ち度が低い可能性があり、当然、販売価格も高くなりません。