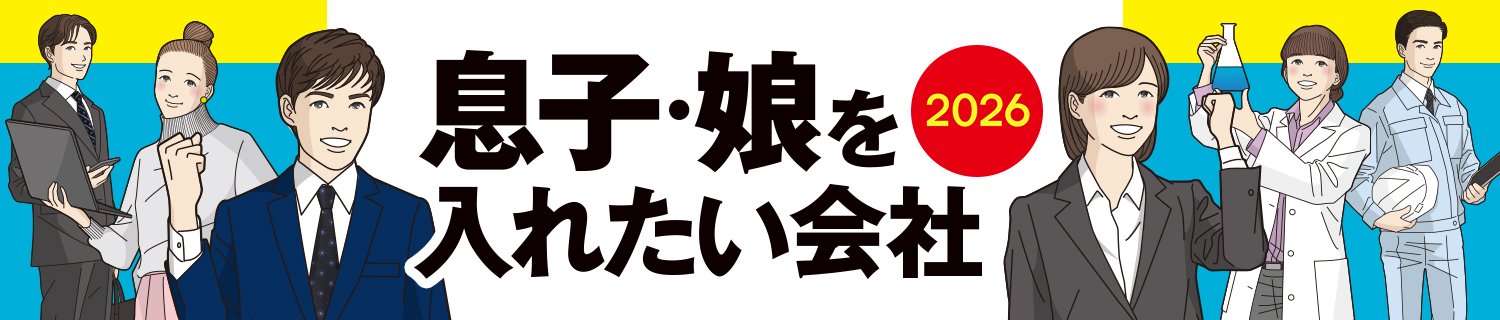2社で筑波大学が1位
採用エリアに特色
武田薬品工業は前回とランキングが大きく変わった。就職者数1位は筑波大学で、2位が慶應義塾大学、3位は千葉大学、東京大学、大阪大学が同順位だった。
6位は岐阜薬科大学と東京理科大学が同順位で、8位は北海道大学、東京農工大学など12校がランクイン。全国の医学部や薬学部がある国立大学から幅広く採用している。私立では薬科大学や早慶の他、創業の地が大阪ということもあり、関関同立勢がランクインした。
アステラス製薬は前回同様、1位は筑波大学だった。23年11月、同社は筑波大学との戦略的パートナーシップを結んでいる。2位は東京理科大学、3位は京都大学となった。
前回2位だった東京大学は4位となり、5位は東北大学など3校、8位は東京工業大学(現・東京科学大学)など5校が並んだ。
中外製薬の1位は前回と同様に東京大学だった。2位は京都大学、3位は九州大学となった。
4位は東北大学と東京理科大学が同順位、6位は大阪大学、7位は慶應義塾大学、8位は北海道大学など3校が並んだ。旧帝国大学が比較的上位にランクインしている。
新薬メーカーが不可避の
「パテントクリフ」
医薬品業界は成長を続けているが、薬価基準の引き下げやジェネリック医薬品の台頭により、新薬メーカーの収益は圧迫されている。
一方で、国はワクチン開発支援やスタートアップへの投資、人材育成などを通じ、創薬力の強化を進めている。
新薬開発は数百億円と10年以上の年月を要し、成功率も極めて低い。そのため、AIやデータ解析の活用による研究開発の効率化が急務となっている。
また、国内市場が頭打ちとなる中、海外、特に米国市場への展開が重要となっており、武田薬品工業のように積極的な海外企業の買収が進んでいる。
医薬品は医療用とOTC(医師の処方箋を必要とせず、ドラッグストアなどで選んで購入できる市販薬)に分かれ、特に新薬は特許期間中に収益を上げるが、特許切れ後は売り上げが急落する「パテントクリフ」に直面する。
これを克服するには、新たな疾患領域に特化した開発が重要であり、企業ごとに戦略は異なる。