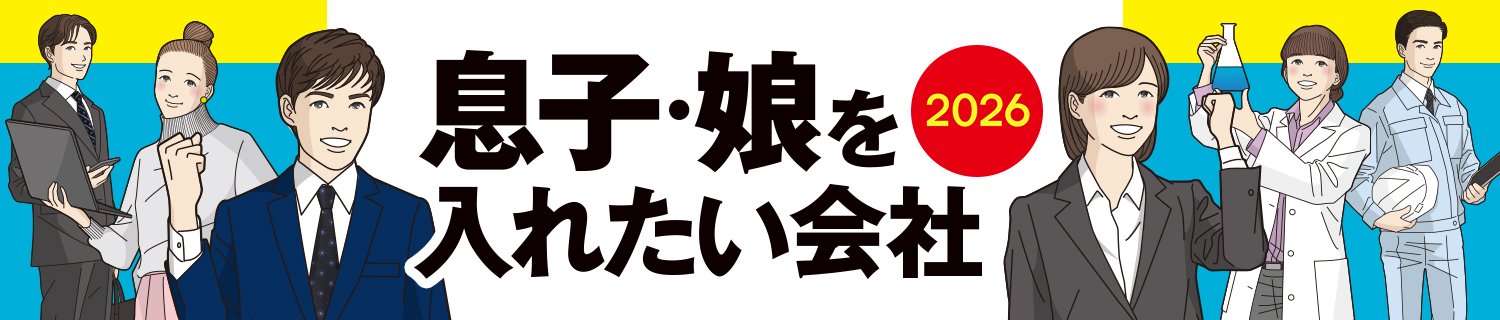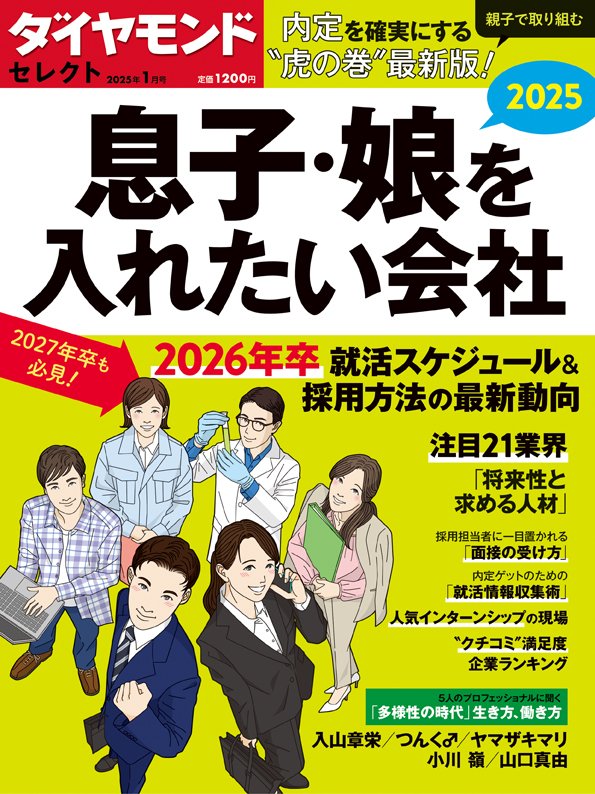製薬会社が欲しがる
“次世代人材”とは?
製薬会社には、営業販売職のほかに、研究職、開発職、生産技術職など多様な職種が存在する。これらの職種に応じて、必要とされるスキルや資格も異なる。
創薬の成功確率を高めるためには、専門人材の確保に加え、AIの活用が不可欠である。従来は動物実験や臨床試験を通じてしか分からなかった薬の効果を、AIによって少ないデータで予測可能にする試みが進んでいる。
しかし、バイオロジーとデジタルの両方に精通した人材は希少であり、製薬業界ではそのような人材を巡る競争が激化している。
医薬品の開発には10年以上の年月がかかるため、業界の動向を短期間で判断するのは難しい。
このため、就職先を選ぶ際には、企業が革新的な新薬開発にどれだけ真剣に取り組んでいるかを見極めることが重要となる。
短期的な業績や新薬の状況だけで企業を判断するのは近視眼的であり、長期的な視点から継続的に新薬を生み出せる企業かどうかを重視すべきである。
企業研究を行う上では、研究開発に対する姿勢、最先端技術の導入状況、優秀な人材の確保・育成の取り組みなどを、ニュースや公式情報から調べる必要がある。
さらに、製薬会社の社員と直接面談することで、企業文化や将来性を感じ取ることができる。
文系・理系を問わず、製薬業界では多様な人材が必要とされているが、特に理系人材の中でも高度な専門知識を持つ者の重要性が高まっている点が、他の製造業との違いである。
創薬の開発スピードが求められる中、企業はバイオロジー、データ分析、エンジニアリングの分野に強い人材を重視しており、AI創薬の進展など、デジタルテクノロジーの活用が今後の鍵となる。
医薬品はライフサイクルが短く、企業業績も変動しやすいため、終身雇用が保証されにくくなっている。
したがって、特定の企業に固執するよりも、業界全体で通用する能力を磨くことが重要である。製薬業界で長く活躍するためには、「会社」ではなく「業界」に就職するという意識を持つことが求められる。
*この記事は、株式会社大学通信の提供データを基に作成しています。
医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。561大学から得た回答を基にランキングを作成した。上位10位以内の大学を掲載。就職者数にグループ企業を含む場合がある。大学により、一部の学部・研究科、大学院修了者を含まない場合がある(調査/大学通信)