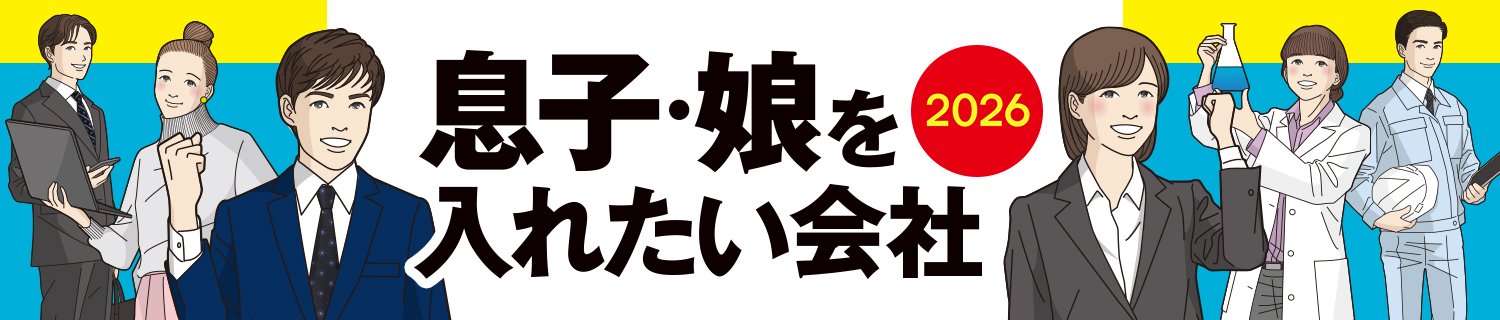2社で日大がトップ
地域性が色濃く反映
JR各社においては、主力事業である鉄道運行の営業エリアがあらかじめ決まっているため、採用活動にも地域性が色濃く反映されやすい傾向がある。
24年の採用ランキングでは、JR東日本の1位は日本大学、2位は早稲田大学、3位は中央大学だった。昨年に引き続き、日本大学の採用数が際立って多く、強さを見せている。
4位には東京電機大学、5位には新潟大学、6位には筑波大学など4校が並んだ。さらに10位には東京大学など5校が入っている。関東および東北地方の大学が上位を占めていた。
JR東海においても、1位は日本大学、2位は早稲田大学となっており、この2校はJR東日本と同様にトップ2を占めた。3位には京都大学がランクインしている。
4位には東京大学と名古屋大学が並び、6位は名城大学、7位には中京大学と近畿大学が並んだ。9位には慶應義塾大学と大阪工業大学が入っている。
同社の主力路線である東海道新幹線は関東・東海・関西を結んでおり、採用もこれらの地域の大学から多く行われている。
JR西日本では、1位が近畿大学、2位が関西大学、3位が関西学院大学だった。
4位には立命館大学、5位には京都大学など4校が並び、9位には大阪公立大学と同志社大学がランクインした。
これらの結果から、関西圏の大学が上位に集中しており、いわゆる「関関同立」と呼ばれる有名私立大学がそろって上位に入っていることがわかる。
「駅で働く」だけじゃない
鉄道会社に求められる人材は?
現在、鉄道業界で注目されているのが、Suicaの多機能化である。もともと運賃決済のためのカードだが、現在では認証機能としての活用も広がっている。
たとえば、24年の能登半島地震では、被災地にSuicaを配布し、本人確認や支援物資の管理に利用された。これはマイナンバーカードの機能が十分に整っていない現状において、Suicaの持つ即時性や信頼性が評価された結果だ。
将来的には、クラウド型Suicaの普及によって、データ処理の迅速化やチャージ上限の引き上げが見込まれている。
これにより、駅インフラに依存しないサービス展開が可能となり、交通系ICカードは決済ツールから社会インフラへと進化する可能性を秘めている。