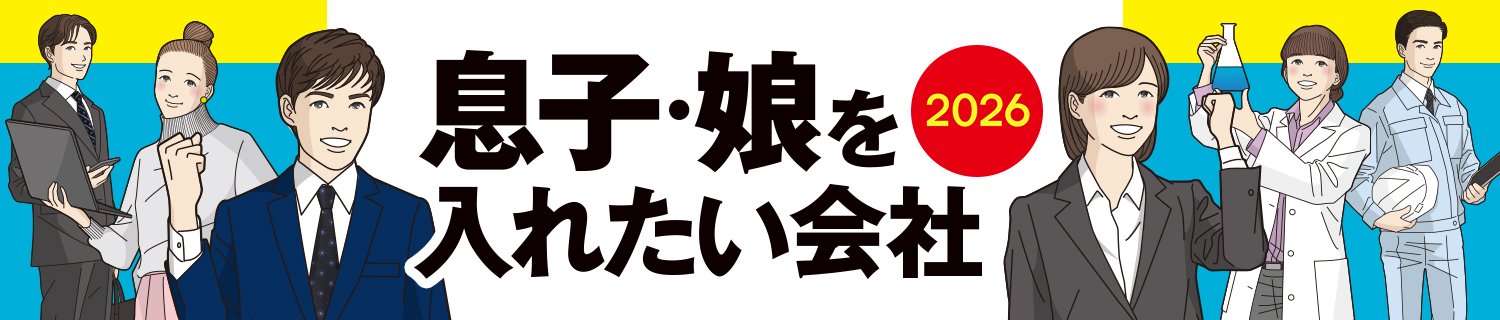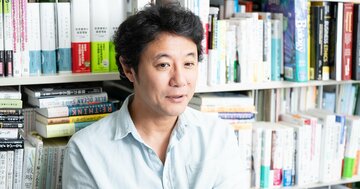イラスト:上坂じゅりこ
イラスト:上坂じゅりこ
内定ゲットのために、避けては通れない「面接」。どんな準備をするべきか、当日はどんなことをしゃべればよいか、そして、服装で気を付けるポイントは――? 累計3000人の学生を面接した経験を持つ元採用担当者が、「面接官の本音」を明かす。(取材・文/フリーライター 友清 哲)
1次面接や2次面接と、最終面接は大きく違う
大手総合電機メーカーでマーケティング担当を務めた後、その知見と目線を生かして大手小売業で新卒採用を担当してきた永島寛之氏。累計3000人弱を面接した経験からまず強調するのは「面接官は、楽しく実りのある会話を求めている」ということだ。
「面接というのは良くも悪くも、受ける側はそれなりの準備をして臨むものです。もちろん、最低限のルールや様式は大切ですが、質問にきちんと答えてほしいというより、その場の“対話”を楽しみたいのが面接官の本音です」
多い時は1日10人ほども相手にしなければならないわけだから、楽しく話ができる人の方が好印象なのは間違いないという。逆に言えば、学生は心地の良いセッションが成立した手応えがあるなら、その面接は成功と言っていい。
とはいえ、学生の側からすれば、どうしても緊張が付きまとう。うまく言葉が出てこなかったり、たどたどしくなってしまうこともあるだろう。それでも「緊張するのは当たり前。だからこそ、そこは度外視して本質的な人柄や能力を見ようとしてくれる会社を選んだほうがいいでしょう」
では、企業がチェックしようとしている「本質」の部分とは何か。これについては面接の段階ごとに、企業側の視点は異なっている。
「最終より前の面接では、これまでにやってきたことや考え方、成長意欲、さらには自社が求めている人材像に近い人物なのかどうかを、さまざまな角度から読み解こうとしています。しかし、最終面接まで進むと“今後”に目が向けられるので、注意が必要です」
つまり、1次面接や2次面接の時点では、自社にフィットする人材であるか否かをメインで見るのに対し、最終面接では入社後の5年後、10年後に活躍してくれるかどうかのポテンシャルが重視されるわけだ。
その意味で、最終面接では「付け焼き刃の言葉は通用しない」と永島氏は明言する。最終面接までは行けるがなかなか内定が出ない学生は、まさにこの点でのアピールに問題があるのだ。企業側は少なくとも、採用した人材にできるだけ長く働いてほしいという前提で面接をしている。
「日頃から、5年後、10年後に仕事で何を成し遂げたいか、どんなキャリアを築きたいかを具体的に考えておくことが重要」
最終面接では会社側の視点が一気に変わることを意識して、それまでに接触した人事担当者に「最終面接を担当するのはどのようなクラスの人物なのか」と聞いておくのも一つの手だという。
一方、ぱっと見の印象で得をすることもあるのか。
「服装はよほどこだわりがないのであれば、変にとがった格好はしない方がいい。余計な減点リスクにしかなりませんからね。一言で言えば、“普通”でいいんです。ここは気合を入れて勝負をするところではあ
実際、服装で目立とうと頑張る学生は毎年一定数いるそうだが、「無理している場合は、似合っていないのですぐ分かる」