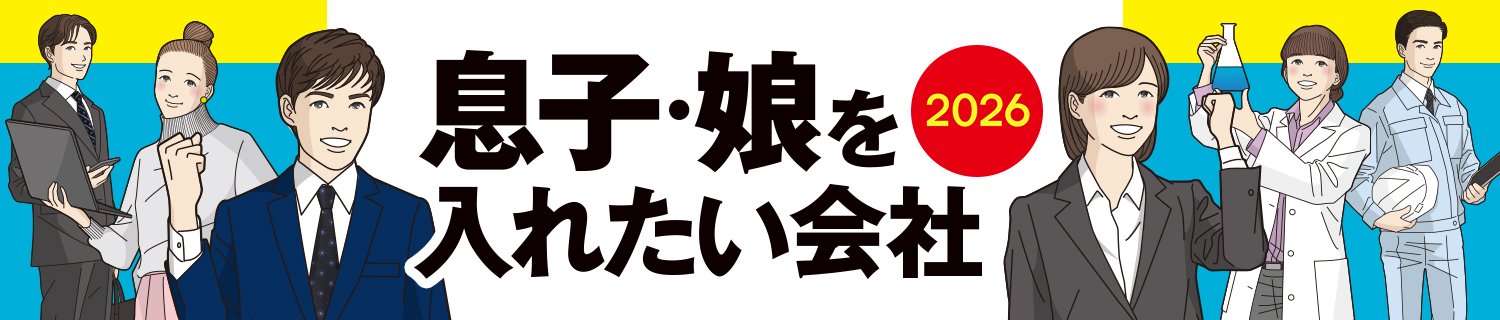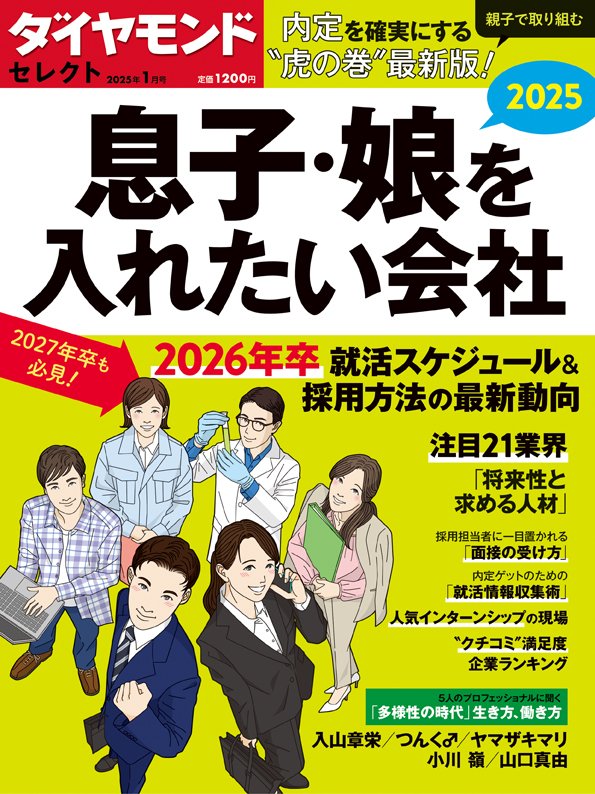そんな中、鉄道業界の人材についても大きな転換点を迎えている。
新卒採用では、安定性を重視する学生から一定の人気を保っているが、将来的な人気低下が懸念されている。
特にJRの不動産部門の社員が他社へ転職する事例が見られ、意思決定のスピードや裁量の広さを求めて他業種へ移る動きがある。
高卒採用においては、夜勤や残業があっても、その分確実な収入が得られるという理由で鉄道業界は依然人気だ。
一方、大卒者には駅業務や運転業務にとどまるキャリアに疑問を持つ人も少なくない。そのため、JR東日本のように、総合職と現場職(エリア職)を明確に分け、希望部署への異動制度などを導入して柔軟なキャリア形成を可能にしているところもある。現場職の採用者にも私鉄の総合職に匹敵するような業務を任せることがあり、実務の幅広さが評価されている。
鉄道業界は国内市場に限界があるため、海外展開にも力を入れている。
日本が提供すべき価値は、車両技術そのものよりも、時間厳守、安全運行、保守管理といった運用ノウハウにある。これらをグローバルに展開することが、日本の鉄道の競争力向上につながる。
国内に目を向ければ、研修制度が整っている一方で、実務経験の幅が限られているため、社員が挑戦する環境が不十分だという課題もある。
今後は希望する部署への異動制度などを通じて、挑戦しやすい職場づくりを進めていけば、他業界からの転職希望者にも魅力的に映るだろう。
また、旧態依然とした企業文化からの脱却を図る動きも出てきている。
そんな中で求められるのは、鉄道業界の固定観念を打ち破り、新たな価値を生み出せる人材だ。古き良き鉄道に思いを馳せるノスタルジーや、マニアックな知識を求める「鉄道オタク」的な視点ではなく、鉄道を地域活性化や社会課題解決の手段として捉える発想が求められている。
鉄道業界では収益の多くを通勤や通学に用いる「定期券利用者」による定期収入が占めるため、利益創出の実感が得られにくく、内向きになりがちな体質も指摘されている。その打破に向け、「駅を防災拠点にする」「無人駅を地域医療や福祉の中心とする」などのアイデアを持つ人材の登用が始まっている。
鉄道会社が社会全体に価値を提供する組織へと進化していく中で、若手にとっての挑戦機会もますます広がっていくだろう。
*この記事は、株式会社大学通信の提供データを基に作成しています。
医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。561大学から得た回答を基にランキングを作成した。上位10位以内の大学を掲載。就職者数にグループ企業を含む場合がある。大学により、一部の学部・研究科、大学院修了者を含まない場合がある(調査/大学通信)