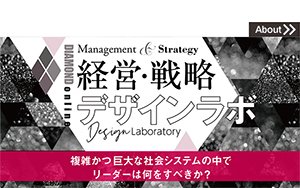変わらぬ「普遍」があるからこそ
「多様性」が生きる
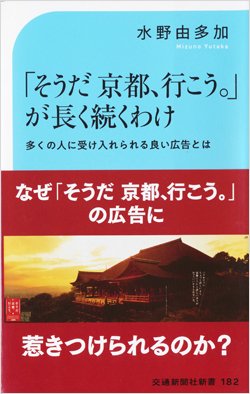 『「そうだ 京都、行こう。」が長く続くわけ-多くの人に受け入れられる良い広告とは』(水野由多加 著、交通新聞社、税込1100円)
『「そうだ 京都、行こう。」が長く続くわけ-多くの人に受け入れられる良い広告とは』(水野由多加 著、交通新聞社、税込1100円)
「そうだ 京都、行こう。」キャンペーンでは、1993年の開始以来、そのキャッチコピーとBGM、そして京都の風景や文化財の美麗な映像という要素は不変のものだ。しかしながら、キャッチコピー以外の広告コピーや映像の素材は毎回変わる。
著者は、この毎回変わる要素について、その時々に「見せたいものを見せてくれる」と指摘している。例えば、東日本大震災が発生した2011年の同キャンペーンは、「本願寺界隈」を取り上げている。京都の東本願寺と西本願寺はいずれも親鸞を宗祖とする浄土真宗の本山だ。浄土真宗でいう「本願」とは「全ての人を救済したいという仏の教え」を意味する。
「本願寺界隈」キャンペーンではコピーで上記のことに触れているわけではないが、震災で被害を受けた人々を「救済したい」という思いが込められていると、著者は推測している。
1993年は伏見稲荷大社が取り上げられ、有名な「千本鳥居」の幽玄な映像がCMで流された。そこにつけられたコピーの一部が秀逸だ。「1200年を行ったり来たり出来る京都です。」――京都の、時代を超越した普遍性を強調している。
現代の旅行は、個別行動が増え、中身も多様になってきている。だが、そこに重石のように普遍的な要素が据えられているからこそ、多様性が「単なるバラバラ」にならずに済んでいるのではないか。
何度も言及して恐縮だが、大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をメインテーマとし、サブテーマにも多様性の要素が多分に含まれている。そしてその北の方角に、時代を経ても変わらない京都がどっしりと構えている。
本書を読み、京都の普遍性と多様性の関係について、ぜひ考えを巡らせてみてほしい。
気をつけたい
一息ついた後の「五月病」
さて、GWは、楽しいばかりではない。この期間の過ごし方について、注意すべき点がある。
4月から入社、異動などで新たな環境で働き始めた人も多いことだろう。多少なりとも緊張する日々が1カ月ほど続き、GWに突入してホッと息をつく。溜まったストレスもあり、連休中には生活リズムが崩れがちになる。そしてGW後半には、「また仕事が始まる」というプレッシャーに苛まれることに。
こうした一連のプロセスで現れやすいのが「五月病」だ。
防ぐためには、できる限り気分を一定に保ちながら、休みを利用して、4月の自分を冷静に振り返り、改善すべきところを明らかにして、前向きに連休明けの準備をすることだ。
リーダーとして新しいメンバーを率いる立場になった人は、自身のリーダーシップを振り返ってみよう。そんな時に役立つのが本書『dare to lead リーダーに必要な勇気を磨く』(サンマーク出版)だ。著者のブレネー・ブラウン氏は米ヒューストン大学の教授で、長年「勇気、傷つきやすさ、恥、共感」についての研究を行ってきた人物だ。