JR東海とJR九州がICOCAに「乗った」ことに筆者は驚いたが、酒井氏は「レール1本でつながっているので、もともとそういう土壌がありました。3社で一緒にやることで、効率的なシステム運営や施策のスピード感が期待できます」と説明する。
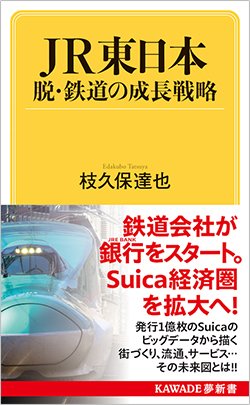 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
モバイルICOCAをベースに作られるモバイルTOICAとモバイルSUGOCAは資金決済法上、ICOCAという扱いだ。ICOCAの名前のまま他社の定期券を発行するのは分かりにくいので、独立したアプリ化した形だが、酒井氏によれば、それぞれにカスタマイズの余地があり今後、独自機能が追加される可能性はあるようだ。
本家の進化も続く。モバイルICOCAは2027年春に、これまで磁気定期券しか対応していなかったICエリア外でもICOCA定期券が利用できるサービスを導入予定で、モバイルSUGOCAにも展開を予定している。こうした機能が充実することで、さらなる普及が期待できるだろう。
乗車券システムは今後、カードに情報を記録せず、端末にライタ機能を必要としない、より低コストのセンターサーバー式へ移行していくが、現時点では新型Suicaを導入中のJR東日本に続く事業者は現れていない。
一方、関東ではJR東日本など8事業者が2026年度以降、関西ではJR西日本が2028年度以降、京阪電鉄が2029年度までにコストのかかる磁気乗車券を廃止してQRコード乗車券に置き換える計画を発表している。QRコード乗車券はセンターサーバー式のシステムであり、現行ICカード乗車券が移行しない理由はない。
だが、人口減少にさらされた地域鉄道・バス事業者には、次世代システムの標準仕様が確定するまでICカード対応を待つ余裕はない。移行期においてICOCAが果たす役割は小さくないだろう。願はくは東日本でも同様の動きが出てほしいところだが、具体化しないのであれば、いっそICOCAの東日本進出があってもいいのかもしれない。







