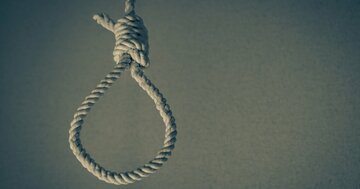子どもといることを
1カ月だけ認められる
出産から6日目だった。花江は知恵子を連れて、ともに健康な状態で、笠松刑務所に戻ってきた。
笠松刑務所の分類と岐阜県の児童相談所が話し合った結果、〈最低ひと月は、刑務所内で子供を育てること〉という方針が示されたのである。乳児をすぐに母親から引き離すのは、〈母子両方にとって好ましくない〉との判断があったらしい。
笠松刑務所の所長は、それを受け入れ、〈1カ月間だけ許可する〉と、乳児の携帯を認めたのだった。
知恵子の立場は、いわゆる「携帯乳児」だ。それは、監獄法12条の1項と2項に規定されている。
〈一項・新たに入監する婦女その子を携帯せんことを請うときは必要と認むる場合に限り満一歳に至るまでこれを許すことを得〉
〈二項・監獄において分娩したる子についてもまた前項の例による〉
このように法律上は、満1歳まで、刑務所内で子供を育てることができる。けれども、現実的には不可能だった。なぜなら、受刑者のほぼすべてが、懲役刑を受けた者だからだ。先進国の中では、日本や韓国など、ごく一部の国でしか取り入れられていない懲役刑。それは、刑務作業に従事することによって罪を償う、という刑罰なのだ。したがって我が国の受刑者は、免業日以外は必ず、刑務作業に就かねばならなかった。
ただし例外として、病人の場合は、作業を免除されることもあった。たとえば、それを出産後の受刑者に適用させるとどうなるのか──。残念ながら、その期間は、1カ月が限度だ。ひと月もすれば、充分に健康体に戻り、作業にも就けると、そう看做されるのである。刑務所内には、作業中の母親に代わり、子供の面倒を見てくれる人などいない。結局、携帯乳児は生後ひと月で乳児院に預けられる、というのが実態だった。
刑務所内の育児室に
受刑者たちの笑い声が響く
1986年の3月も、後半に差しかかり、知恵子がここにいられる時間も、あとわずかになった。恵子が産休に入るのも、もうひと月後だ。
育児室は、病舎内に設けられていた。その6畳の部屋には、いろ紙やちり紙でつくった飾りつけが、いくつもあった。花や動物の形をした折り紙など、どれも、看病婦の受刑者がつくったものだ。
恵子が、育児室内で、知恵子を抱かせてもらっていると、看病婦たちが冷やかしてくる。
「高田先生が、育児の練習してみえるわ。でも、抱き方へたくそで、見てられんわ」
「ほんまや。なあ知恵子ちゃん、本物のママのほうがええな」