政府が対応すべきなのは
「全体」ではなく「個別」
日本経済が今後、高度成長期や安定成長期のような勢いを取り戻す可能性は低い。国民生活の基盤を固めるためには経済成長は必須だが、2〜3%の経済成長を持続的に達成するのは困難だ。
1990年代以降、政府や国民は「経済学の思考法」の下で努力を続けてきたものの、十分な結果を残せなかったのはすでに述べた通りだ。
個人も政府も精一杯、努力しているのになかなか結果が出ず、いらだちが増す。「生活が苦しい」と感じている多くの人々が、「景気は回復している」と説明する政府に不信感を募らせるのも無理はない。
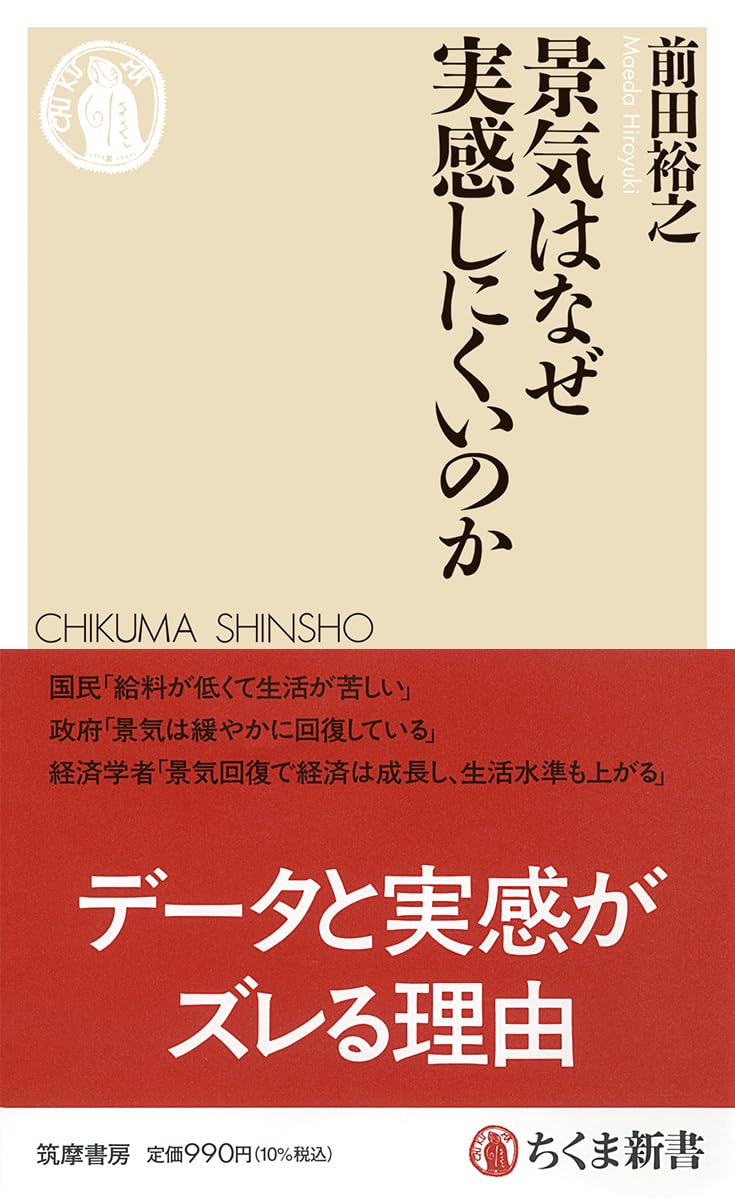 『景気はなぜ実感しにくいのか』(前田裕之、ちくま新書)
『景気はなぜ実感しにくいのか』(前田裕之、ちくま新書)
袋小路から抜け出すために、まず変わるべきなのは、政府および政府を統率する立場にある政治家だ。政府支出を増やし、全体を底上げすれば多くの国民に恩恵が行き渡るという安易なケインズ主義が通用しなくなっていることは90年代以降の日本経済を見れば明らかだ。
日本型不平等社会の中で苦しんでいるのは、どこに住み、どんな働き方や暮らし方をしている人たちなのか。税や社会保険料の負担感が大きいのはどんな世帯なのか。
政府に求められるのは漠然とした「全体の底上げ」ではなく「個別の対応」、さらには「個別対応を可能にする制度の設計」であろう。日本型平等社会を前提にした税制や社会保障制度の再設計も急務だ。
政治家にとって「全体の底上げ」は楽な選択肢なのだろう。政府の財政赤字が拡大し、公的債務が膨らんでも、自らの懐が痛むわけではない。
国民から「効果が乏しい」という声が出るかもしれないが、経済対策そのものに反対する声は出づらい。それに比べると、個別の対応をすれば、除外される人から不満の声が出やすい。
行政にとっても「個別の対応」は限りなく骨が折れる仕事だ。データの収集も含めて行政事務が増え、現在の体制のままでは仕事をこなしきれなくなる恐れもある。
しかし、こうした方向に政策や制度を転換していかない限り、日本型不平等社会の中で苦しんでいる人たちは「生活が苦しい」と訴え続けるだろう。







