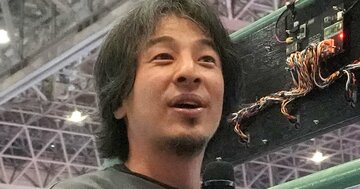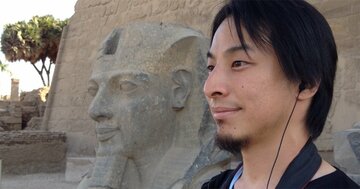つまりひろゆきはこの番組において、どのような問題についても、どのような立場であっても、相手を論破してみせているのである。このように、不利な状況をはねのけて安定した勝率を維持している点に、ひろゆきが「論破王」と称される所以があるのだろう。
特定の立場に
こだわりがなくても勝つ
同時に、議論の場がこのように設定されているがために、それは彼自身に特定の立場へのこだわりがない、ということも露呈させる。言い換えるなら、彼には自分自身の主張がない、少なくともそれを議論の場でまったく表明していない、ということだ。
それに対して、彼の対戦相手はしばしば自らの信念に基づいて主張するが、しかし論破される。そのため、何の信念も持たない者が、信念を持つ者を論破してしまう、という光景を、視聴者は目の当たりにすることになる。
もちろんこれは、ディベートという討論の形式に特有のものではある。しかし彼の場合、この番組の企画に限らず、およそどのような議論においても、それをディベートのように捉え、あえて相手と対立する立場を取り、そこから相手を論破しているように思える。
彼が絶大な支持を得ているのは、そうした論破を、人々が彼に期待しているからだ。つまり人々は、何かの信念を持つ者が、何の信念も持たない者に論破される光景を、待ち望んでいるのである。その背景にある欲望は、いったい何なのだろうか。
おそらくそれは、信念を持つ者へのある種の不信感なのではないだろうか。口では信念を語る人間に垣間見える、自己欺瞞(ぎまん)への嫌悪感ではないだろうか。あるいは、信念によって自己を正当化する人間が、実はまったく非合理的なのではないか、という疑念なのではないか。
信念を持ったところで、結局のところ、信念を持たない者を納得させることなんてできないし、またそうした者に簡単に論破される。したがって、もっともらしく信念を掲げることは、まったく無意味なことだ。ひろゆきは、そう思いたがろうとする欲望に、論破によって応えているのではないだろうか。
ひろゆきが本当に
説得しようとする相手
では、なぜひろゆきは、そのように明らかに不利な条件のもとで、相手を論破することができるのだろうか。
彼は、論破の「必須アイテム」として、さしあたり「論理」と「事実」を挙げている。どれほどしっかりとした論理に基づいていても、そこで語られている事実が虚偽であれば、相手を説得することなどできない。