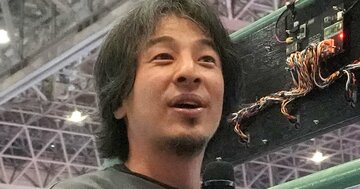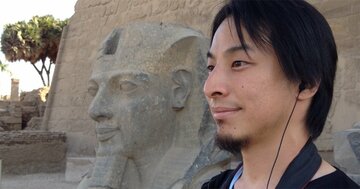あるいは反対に、たとえ事実に基づいて何かが語られるのだとしても、論理が破綻していれば、同様に説得力のある主張をすることはできない。したがってこの二つは、説得において欠かすことができない条件なのである。
ただし、こうした論破のための材料が揃っているのだとしても、誰に向けて語るのかを見誤れば、それを有効に活かすことはできない。そして興味深いことに、相手を論破しようとするとき、自分が論破しようとする相手に向けて何かを語ることではなく、その議論の勝敗を判定する権威を持つ者に対して語らなければならない、と彼は主張する。
要するに、「論破力=説得力のある話し方」なのですが、その説得力をどう高めるかというのは、議論している直接の相手に対してではなくて、議論を見聞きしている周りの人に対して高めていくものなのですね。
(『論破力』西村博之、朝日新書、2018年)
ひろゆきは、相手を論破するとき、相手に向かって語っているのではない。彼が本当に説得しようとしているのは、その議論をジャッジしている第三者なのである。
なぜ第三者を
納得させようとするのか
ここに彼のコミュニケーション観の大きな特徴がある。すなわち論破とは、自分が議論している相手を説得することではなく、そこで自分が相手を論破したということを、第三者に認めさせることなのである。したがって、議論をしている相手が説得されるか否かは、彼にとって本質的に問題ではない。
もしかしたら、相手は議論が終わっても、決して自分が論破されていない、説得されてはいない、と主張するかも知れない。しかし、そうであったとしても、その議論においてひろゆきが相手を論破した、と第三者に認められるのであれば、それは彼にとって論破なのである。
論破の成否が、あくまでもそれを認める第三者の判断に基づくのだとしたら、その第三者がどのような人物であるかによって、何をどのように語るのかもアレンジされる。
たとえば、第三者が社会的な弱者であれば、そうした人が共感しうるように語るだろうし、それが子どもであれば、子どもでも分かるような簡単な言葉で説明するだろう。