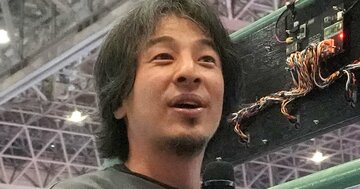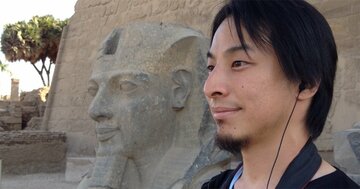またひろゆきは、そもそもそうした第三者が存在しない状況では、議論すること自体を避けている、とも語っている。要するに、相手と1対1で議論しないということだ。なぜならその場合、相手が決して論破されたことを認めなかったとしたら、事実上、相手を論破することは最初から不可能になってしまうからである。
彼は議論において、相手から認められたいと思っていないし、そもそも理解されたいとすら思っていない。それが、議論における彼の怪物のような強さの背景にあるのではないだろうか。
論破の根底は
「面白そうだからやってみよう」
ひろゆきは、議論において相手からどう思われるかということに、そもそも関心を持っていない。だからこそ彼は、相手から嫌われたり、怒られたりすることも、まったく意に介さない。それどころか、議論を有利に進めるために、意図的に不愉快な言動をして、相手からの嫌悪感を誘発し、相手を感情的にさせることもある。彼は次のように述べる。
(『論破力』西村博之、朝日新書、2018年)
彼にとって議論は、仮説を検証する遊びに近いものである。議論の目的が相手を論破することであるとすれば、相手がどのような言動をするのかを予測し、その一手先を読んで、相手を詰ませることができなければならない。
どうやら彼は、議論が開始される時点で、相手の言動について一定の仮説を構築しているようだ。その仮説は、最初は開かれたものだが、やり取りを繰り返すなかで、徐々に限定された振れ幅のないものへと確証されていく。彼は、そのプロセスに面白みを感じるという。
ただしそれは、議論の相手を理解するために行われるのではない。彼が関心を持っているのは、あくまでも第三者に論破を認めさせることであり、相手と互いに理解し合うことではない。
したがって、こうした仮説の検証も、あくまで相手を自分が向かわせたい帰結へ、つまり相手が袋小路に陥って敗北する未来へ誘導するために、行われる。そしてそこに、彼が他者と議論しようとする動機がある。