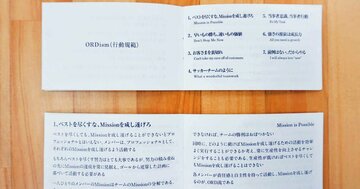「パーパスおじさん」が
「プリンシプルおじさん」に鞍替え!
筆者はこれまでに、100社を超える企業のパーパス策定と浸透をお手伝いしている。「パーパスおじさん」を自称してきたが、最近は「プリンシプルおじさん」に鞍替えしている。パーパスは、実践(プラクティス)されてこそ価値がある。そしてそのためには、一人ひとりが改めて「プリンシプル」に立ち返らなければならないはずだ。
「Practice makes perfect」という英語のことわざがある。「継続は力なり」と訳されることが多い。プリンシプルも、まさにプラクティスを繰り返すことで、身についていく。しかし、実は「パーフェクト」という最終の姿には、いつまでも到達することはない。日本流の武道や芸能にも「段級位」があるが、10段という最高位に上り詰めることはない。
道元禅師は主著『正法眼蔵』の中で、「道無窮」を唱えた。「道は窮なし」と読む。道はどこまで行っても終わりはないという意味である。道元は「仏道」のことを語っているが、これは日本流の「○○道」にはすべからく当てはまる教えである。
「パーパス道」も同じだ。シリコンバレーでは、「MTP(Massive Transformative Purpose)」という言葉が好んで使われる。「巨大で革命的なパーパス」という意味だ。「北極星」とも呼ばれる。筆者は、これを「星座群(Constellations)」と読み替えている。
そもそも北極星は、北半球でしか見えない。しかも、「不動の一点」である。それだと、画一的で全体主義に堕してしまう。それより、好きな星座を思い思いに心に描き、そちらを目指していくほうが、ずっと多様性に満ちている。同じような方向であれば、少なくとも途中まではほかの「同志」たちと一緒に向かえばよい。
目的(パーパス)の星にたどり着いたとしても、そこではまた、行きたい星がはるか先に広がって見えるはずだ。いま掲げているパーパスは、けっして最終ゴールではない。一時の経過地にすぎず、その先へとつながっていく。
パーパスという言葉の語源をひも解くと、ラテン語の「pur(前に)」と「pose(置く)」という言葉が組み合わさったものだという。「物事を達成するために目の前に置く」ことから、「目的」を意味するようになったらしい。だとすれば、目の前に置くパーパスは、次なる高みへと進化し続けてもいいはずだ。