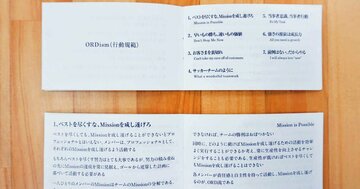Photo:3D_generator/Gettyimages
Photo:3D_generator/Gettyimages
京都先端科学大学教授/一橋ビジネススクール客員教授の名和高司氏が、このたび『シン日本流経営』(ダイヤモンド社)を上梓した。日本企業が自社の強みを「再編集」し、22世紀まで必要とされる企業に「進化」する方法を説いた渾身の書である。本連載では、その内容を一部抜粋・編集してお届けする。今回は、企業が掲げる「パーパス」に着目。書籍『パーパス経営』の著者でもある名和教授が、企業が立派な志(こころざし)や存在意義を策定したにもかかわらず、ビジネスの現場で体現・実践できない要因を深堀りしていく。
立派なパーパスを謳いながら
何も実現できずに終わる企業が続出
2021年に筆者は『パーパス経営』 (東洋経済新報社)を上梓した。企業が「パーパス」を掲げることは、いまや世界的な潮流になっている。まさに「パーパス狂騒曲」とでも呼ぶべき盛況ぶりである。それ自体は、パーパスを仕掛けた一人として喜ぶべきことなのかもしれない。
しかし、実際には大変心配になってくる。立派なパーパスを謳いながら、それだけで終わっている企業が後を絶たないからだ。
それでは、ひと頃のESGウォッシングやサステナビリティ・ウォッシングと同様、形だけパーパスを掲げる見せかけのパーパス・ウォッシングに終わってしまう (ウォッシュには「メッキ」の意味がある) 。
パーパスは未来の「ありたい姿」である。言わば「きれいごと」にすぎない。それを実践しようとすると、途端に現実の壁に直面する。そうでなければ、とっくに実現されているはずである。パーパスを実践に移そうとした瞬間に、「できない理由」が厳然と立ちはだかるのだ。
パーパスを実践(プラクティス)に移そうとする時、この理想と現実のギャップをいかに埋めるかが本質的な課題となる。現実の問題は、あちらを立てればこちらが立たず、という二律背反に陥りやすいからだ。
 PHOTO (C) MOTOKAZU SATO
PHOTO (C) MOTOKAZU SATO京都先端科学大学 教授|一橋ビジネススクール 客員教授
名和高司 氏
東京大学法学部卒、ハーバード・ビジネス・スクール修士(ベーカー・スカラー授与)。三菱商事を経て、マッキンゼー・アンド・カンパニーにてディレクターとして約20年間、コンサルティングに従事。2010年より一橋ビジネススクール客員教授、2021年より京都先端科学大学教授。ファーストリテイリング、味の素、デンソー、SOMPOホールディングスなどの社外取締役、および朝日新聞社の社外監査役を歴任。企業および経営者のシニアアドバイザーも務める。 2025年2月に『シン日本流経営』(ダイヤモンド社)を上梓した。
たとえば、CSV(Creating Shared Value/共有価値の創造)をパーパスで謳っていても、実際には社会に還元するのか、それとも自社の利益とするのか、判断を求められる局面がほとんどである。また、マルチステークホルダー主義をパーパスで掲げる企業であっても、実際には顧客と社員、あるいは株主の中で、誰の便益を最優先するのかという判断を迫られるケースが後を絶たない。
現実の世界でパーパスを実践(プラクティス)するためには、さまざまな場面において判断するための軸が必要となる。それを筆者は、「プリンシプル(原理原則)」と呼んでいる。パーパスという「きれいごと」をプラクティスするためには、プリンシプルが不可欠となる。