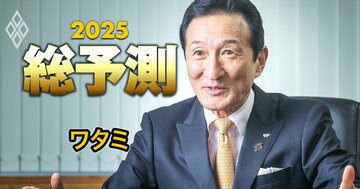Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
外食産業は、スキマ時間に働けるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)を活用する代表的な業界だと考えられている。ところが、大手外食企業での活用はほとんど進んでいない。人手不足が常態化している外食各社が、スキマバイトに対して腰が引けてしまう理由は何なのか。特集『スキマバイト 光と影』の#4では、外食各社の胸の内を探った。(ダイヤモンド編集部 片田江康男、大日結貴)
コロナ禍明けに陥った超人手不足
救世主になりかけたスポットワーク
新型コロナウイルス禍が明けた2023年5月以降、外食産業は国内景気の上昇にインバウンド需要が加わったことで客足が急回復し、深刻な人手不足に陥っていた。日本フードサービス協会によると、23年の外食産業全体の利用客数は前年比6.3%増、中でも「パブレストラン/居酒屋」は24.0%増、「ディナーレストラン」は16.5%と高い伸びとなった。
当時、店舗運営の要であったパートやアルバイト従業員は、コロナ禍で勤務シフトを白紙状態にしていたため、外食各社は客足の戻りに合わせた勤務体制の整備が追い付かず、店を開けたくても開けられない事態に陥った店もあった。
そんな右往左往する外食企業の一助となったのが、単発・短時間で手軽に働きたい人と企業をマッチングさせるスポットワーク事業者だった。それは24年12月に連合が実施した「スポットワークで従事したことがある仕事の内容」の調査にも表れており、「飲食店スタッフ」は2番目に多く、中でも10代は34.5%が従事していると回答。ここには大学生のアルバイトが多く含まれるとみられる。
ところがその後、外食産業においてスポットワークの活用は遅々として進まなかった。
多くの外食チェーンが二の足を踏む中で唯一、スポットワークの活用に積極的なのが、居酒屋「三代目鳥メロ」などを展開するワタミだ。同社は25年4月、スポットワーク最大手のタイミーと業務提携を締結。展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」の直営店で、タイミーを通じて働き手を採用することを決めた。東京・新宿西口ハルク店は、店長から従業員まで全てタイミーを使って雇用した「フルタイミー」店舗である。
それにしてもなぜ多くの外食チェーンは、スポットワークの活用に腰が引けてしまうのか。背景を探ると、外食企業特有のリスクと、トラウマが浮かび上がってきた。次ページで外食企業各社の本音を紹介する。