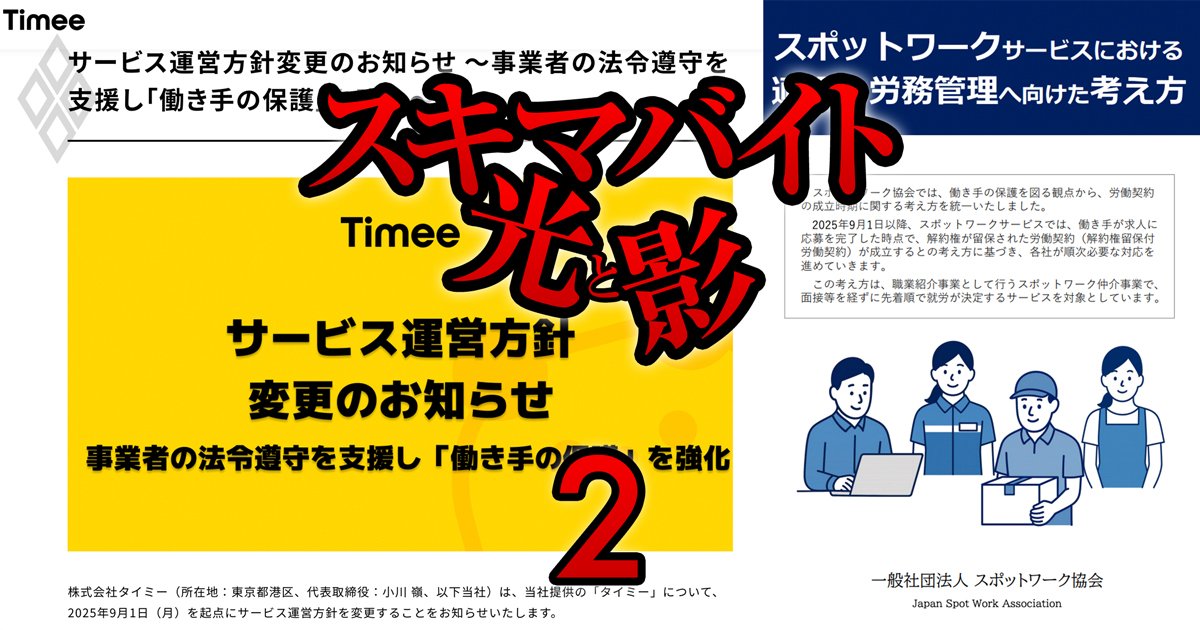
単発・短時間で手軽に働けるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)市場に対し、厚生労働省が労働者保護の観点から包括的な対応に乗り出した。これを受けて、スポットワーク仲介事業者も表向きには「適正化」への対応を進める姿勢を見せている。しかし実際には、自社のビジネスモデルを守るために、裏ではさまざまな“抵抗策”を講じていることが明らかになってきた。特集『スキマバイト 光と影』の#2では、そうした対抗策の中身について図解を交えて詳しく解説する。こうした動きが現実のものとなれば、厚労省が周知したルールが実効性を失い「骨抜き」になる恐れまで出てきている。(ダイヤモンド編集部編集長 浅島亮子)
スポットワークにトラブル多発
厚労省が異例の注意喚起
短時間・単発で働く「スポットワーク(いわゆるスキマバイト)」市場で労務トラブルが相次いでいる。こうした状況を受け、厚生労働省は7月4日、「スポットワークの留意事項」と題したリーフレットを公表し、労働者保護に向けたルールの徹底に乗り出した。
対象となったのは、スマートフォンの雇用仲介アプリを通じて企業と働き手をマッチングするタイプのスポットワーク。働き手(スポットワーカー)は、紹介された企業と直接労働契約を締結する。したがって、労務管理など雇用に関する責任は、あくまでも紹介先企業にあり、スポットワーク仲介事業者には雇用責任はない。
厚労省は、主なスポットワーク仲介事業者であるタイミー(サービス名:タイミー)、パーソルグループ(同シェアフル)、メルカリ(メルカリ ハロ)などが加盟する業界団体「スポットワーク協会」と事前に水面下で調整を重ねてきた(詳細は、本特集の#1『タイミーなど「スキマバイト」の事業者と利用企業に訴訟リスク浮上!厚労省が無法地帯にメスで休業・労災補償発生も』参照)。
今回のリーフレットで特に注目されるのは、「労働契約の解約」、つまりキャンセルに関する注意点だ。企業が安易に契約をキャンセルした場合、損賠賠償や休業補償の支払いを求められるリスクがあるし、スポットワーク仲介事業者にも責任の一端が問われるリスクもある。またこれは、急成長してきたスポットワークのビジネスモデルの根幹を揺るがす問題でもある。
厚労省の方針を受けて、表向きにはスポットワーク仲介事業者も「適正化」への対応を進める姿勢を見せている。しかし実際には、自社のビジネスモデルを守るために、さまざまな“抵抗策”を講じていることが明らかになってきた。
次ページでは、これらの対抗策の中身について図解を交えて詳しく解説していく。現実のものとなれば、厚労省が周知したルールが実効性を失い、「骨抜き」になる恐れまで出てきている。







