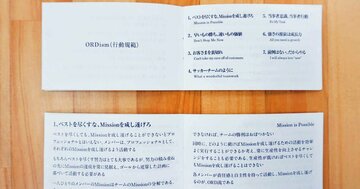「世界標準経営」など
どこにも存在しない
たとえばアメリカにおいてすらすでに時代遅れになっている理論を、「世界標準」として奉る風潮。そもそも、世界標準経営などというものはどこにも存在しない。それは舶来モノに飛びつきやすい卑屈な日本人の島国根性が生んだ幻想でしかないのである。筆者はそれを「擬態病」と揶揄している。コスプレ病と呼んだほうが分かりやすいかもしれない。
そして政府が繰り出すさまざまな「日本の産業と企業の競争力強化策」。最近でいえばガバナンス改革、人的資本強化、スタートアップ支援など。いずれも実効力がないばかりか、産業や企業の競争力をますます弱体化させる掛け声にすぎない。
それでも性懲りもなく、2024年6月には経済産業省の製造産業局が中心となって、「グローバル競争時代に求められるコーポレート・トランスフォーメーション」と題した報告書を出している。いままでさんざん議論されつくした論点と処方箋のオンパレードだ。
これで日本が復活するようであれば、世話はない。しかし、これではまたぞろ経営の最前線を理解していない政府の余計な口出しに終わってしまうのがオチだ。イケていないところを挙げるときりがないが、そもそも議論のスタートが大きく3点間違っている。
第一に、ひと昔前のアメリカ流の経営モデルを「ワールドクラスの経営」と祭り上げ、それとのギャップを埋めようとしていること。アメリカにおいてすらこのようなステレオタイプな議論は10年古く、かつ、それ以外の国の優れた経営モデルを学習すらしていない。もっともこれまで論じてきた通り、ワールドクラスに追いつこうという卑屈な姿勢そのものがナンセンスなのである。
第二に、日本の本質的な特性をまったく理解せず、現場力に裏打ちされたすり合わせ型のディープテック(社会課題の解決など、社会にインパクトを与える科学的発見や革新的な技術)のみを成功モデルとしていること。この議論はすでに20年古い。製造産業局だけで議論すると、このような論点から抜けきれないのだろう。これでは日本の製造業が地盤沈下するのもうなずける。
民間から参加している委員のメンバーを見ても、CFO、CIOなどの本社スタッフ部門が中心。これでは「あったらいいな」といったレベルの空虚な議論に終始してしまうのも無理はない。なぜ、日立製作所、ソニー、ファーストリテイリング、キーエンス、リクルートなどといった勝ち組の日本企業の声を聴こうとしないのか。もっともそのような企業は、ハナから政府主導の論議には興味がないかもしれない。
第三に、そもそも日本の産業と企業がいかに勝つかを論じていること。世界の産業はとっくにグローバルにつながっており、勝ち組日本企業の実態はすでに日本を離れている。国益を守ろうとする政府の気持ちは分からないではないが、そのような「国策」が、とうの昔にグローバル連結している実態から大きく乖離している。