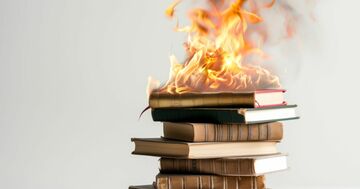興国同志会は平沼を会長に迎えて国本社に改称され、竹内は右翼の中心的人物になった。国本社は平沼の人脈を生かして、軍人、官僚、学者、作家らをメンバーに加え、右派の一大勢力になった。そして竹内が法政に迎え入れたのが、陸軍大将の荒木だった。
38年には、コミンテルンの指示により日本で反ファシズムを呼びかけたとして政治家や大学教授が一斉検挙され、後に無罪になる人民戦線事件が起きる。 法政では、天皇機関説で弾圧を受けた美濃部達吉の長男で、マルクス経済学者の教授、美濃部亮吉らが検挙された。大学はすぐに美濃部を休職処分とし、ほどなく解任した。以降、法政の学内は戦時色一色なった。
言論封殺に発展した漱石門下生の争い
戦後は追放された元総長が復帰
法政騒動で辞職した野上豊一郎の妻は小説家の弥生子だが、卒業生らが竹内を押し上げた背景について、「民族主義的なものがあったのでしょう。自分たちは法政で生まれ育ったのだから、大学運営はすべて卒業生ですべき。一高、東大、漱石門下生は出ていくべきだという考えでしょう」と振り返っている。
当初は漱石門下生の間の争い、そして大学運営の主導権をめぐる分裂が言論封殺の事態にまでになったのだ。
戦後の揺り戻しは激しかった。学生は竹内排斥運動を始め、1週間のストライキを決行。竹内の自宅を訪れて辞任を勧告する者もいた。竹内に近い教授の追放運動も起き、竹内は総長を退任する。
後任に復帰したのは法政騒動の当事者になった野上だった。「国破れて山河ありと言うが、人もある。諸君がそれである。裸一貫で出直す覚悟が必要である」と学生に訴えた。野上の後は、大内兵衛、有沢広巳が総長を引き継いだ。いずれも東京帝大でマルクス経済学を学び、人民戦線事件で検挙された人物だった。戦後の法政大学は、再びリベラル色の強い大学として歩んでいくことになる。