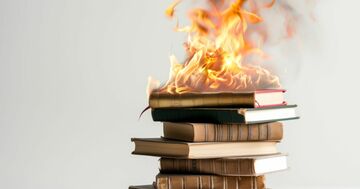大学は左翼系団体の一掃を図ったが、学生は33年に起きた京大滝川事件でも活発に動いた。滝川幸辰教授の処分に反対する大学横断の「大学自由擁護連盟」が結成され、結成大会には125人の学生が参加した。京都帝大から24人、東京帝大から16人、明治から12人が出て、大会副議長には明大雄弁部の学生が選出された。
結成大会当日の朝、戦後横浜市長や社会党委員長になる飛鳥田一雄も拘束された。ガリ版を刷る程度で、本人は「なんとなく左翼」だったと振り返っているが、学生運動が活発だったことは間違いない。
鵜沢総長時代は戦時色に染まる
教学刷新評議会に呼応し靖国参拝まで
だがそんな明治でも 34年に総長に就任した鵜沢総明時代には戦時色に染まっていく。天皇機関説事件を受けて、文部省は1935年、教育に対する統制を強化する教学刷新評議会を設置した。天皇中心の国体を教育現場に徹底する狙いだが、明治からは総長の鵜沢が委員として加わった。
鵜沢は今の千葉県茂原市に生まれ、東京帝大法科大学を卒業して弁護士となり、明治大学法学部長、立憲政友会の衆議院議員、貴族院議員を務めた。明治大学総長を戦前と戦後に計4期務めた異色の経歴を持つ。大正期は吉野作造の民本主義に近い思想だったが、次第に国家主義的な姿勢に変わった。
鵜沢は教学刷新評議会の動きに呼応して、36年に「明治大学振興委員会」、37年の日中戦争勃発後には「皇軍後援会明治大学報国会」を発足させ、自ら会長になった。軍人を支援するため、本来なら大学から支出する必要のない、現在の価値で100万円以上とみられる慰問費を献金し、校旗を先頭に総長、大学幹部、学生らが明治神宮や靖国神社に参拝。天皇の御真影と教育勅語の授与を文部省に申請した。
38年、総長に明治大学初代校長で「清濁あわせ飲む、偉大な包容力」と評された木下友三郎が再任されると、大学幹部に警察官僚と軍人を招き入れた。大学理事にはそれまで、司法畑や実業人から就任していたが、明治大学OBで内務省に入り、各県の警察幹部を歴任した双川喜一が、専務理事になった。