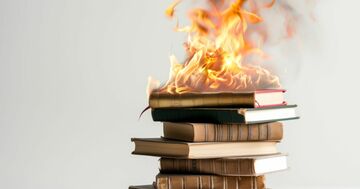学生運動が活発だった明治
「植原・笹川事件」では警察が出動
明治大学の起源も、1881年に開校した明治法律学校だった。明治政府が司法官僚養成のために設置した司法省法学校の1期生で、ボアゾナードらの講義を受けた、いずれも20代後半の岸本辰雄、宮城浩蔵、八代操の3人が創立者だった。
3人のうち2人は早世し、学校の中心になったのは岸本で、初代校長に就任する。明治大学に改称した1903 年には「明治大学の主義」という演説をし、「学問の独立、自由を保ち、自治の精神を養い、人格の完成を図る」と訴えた。
同じ自由な校風の法政が、政治色の比較的薄い穏健な路線だったの対し、明治は大正デモクラシーや普通選挙運動が展開されていた社会の雰囲気に学生も呼応し、学生運動も活発だった。
1920~21年に起きた「植原・笹川事件」は、学部昇格を見送られた政治学科の学生が、学長らの退陣勧告を決議したことが始まりだった。
大学当局は、学生リーダー8人を放校処分とし、学生に同調したとして教授の植原悦二郎と笹川臨風を解職した。これに学生らが猛反発し、文部省を巻き込み、警官も出動する事態になった。
『明治大学百年史』は、当時、東京朝日新聞に掲載された記事の49本にも及ぶ見出しを紹介している。21年5月31日の見出しは「学生と警官大乱闘して流血の騒動演ず 学長以下辞職して明大遂に瓦解」と激しい。
だが1925年の治安維持法の公布などを機に、共産主義思想の学者や共鳴する学生らに対する政府の締め付けを受けるようになり、学内の共産党系組織も摘発された。当時のデータは乏しいが、32年の5.15事件の直後には同法違反で明大生37人が検挙された。3人が放校、16人が停学の処分を受けた。