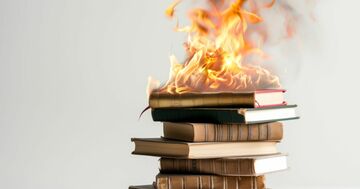法政では学内の統制が強まり自由な校風が消えるきっかけとなった。騒動の収拾の調停役として学内の実権を握ったのが竹内覚久治だった。校友で右翼勢力の中心人物だ。
法政卒業生らが、漱石門下の法政大教授には東京帝大出身者らが多いことから、騒動を機に東京帝大の影響がさら強まると危機感を持ち、竹内をかついだ。竹内は学内の締め付けを図るとともに、右翼団体・国本社をともに担っていた陸軍大将の荒木貞夫を大学顧問として招いた。
陸軍大臣を経験、陸軍皇道派の代表格だった荒木は、1937年、日中戦争が始まると、予科で修身を教え始めた。荒木はその後、近衛内閣の文部大臣に就任して全国の学校に「皇道教育」を徹底、軍事教育を強制するなど大学の思想弾圧の先頭に立つ。そして竹内は43年には卒業生で初めての総長にまで登りつめた。
「法政騒動」は学内の主導権を右翼勢力が握り軍幹部を招き入れて大学が戦時体制に組み込まれていく契機となった。法政と創設の経緯や校風でも共通するところが多い明治大学でも、「植原・笹川事件」と呼ばれる騒動が起きている。そしてその後、大学の空気が戦時色に染まっていった。
学内に軍人や警察官僚が招き入れられ、自由な言論が封殺されていった流れでも両校は共通している。
共通点が多かった法政と明治
法曹家が創設し民権拡張に尽力した経緯
両校は創立時期が、法政1880年、明治81年と近いだけでなく、ともに3人の若い法曹家が、近代国家の基礎を担う法律専門家を養成するため設立した。
近代国家の仲間入りを果たし、当時の明治政府の最大の外交課題だった不平等条約を改正する条件として、法律制度の整備と法律の実務家の要請が急務だった。東京六大学の私立大学の半数が法律専門学校を前身とするのも、こうした時代背景と無縁ではない。