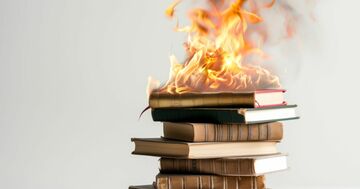両校は神田界隈を拠点にして競争し、合併話もあった。フランス法の専門家で、外国人教授、ボアゾナードの影響を受けている。ボアゾナードは、明治政府がヨーロッパで評価の高いナポレオン法典をモデルにするため、日本の法整備にふさわしい人材として白羽の矢を立て、日本に招聘した。自然法主義者だが、国家の実情にも配慮した法制定が必要だと訴え、刑法と民法の制定に影響力を発揮した。「日本近代法の父」と言われる。
両校は私立学校として自由や権利、進歩を掲げて民権の拡張に力を入れたことでも共通している。法政は、1913年から31年まで学長を務めた松室致がリベラルで穏健な校風を目指したことで、自由の気風で知られた。その精神を体現していたとして語られるのが、哲学者で教授を務めた三木清と戸坂潤だ。
三木は和辻哲郎の後任として教壇に立ち、代表作『人生論ノート』などで幸福や希望のメッセージを戦時中も発信した。戸坂は科学論やイデオロギー論の著作で知られた。ともに治安維持法で検挙され、獄中で死亡する。戦後、学生自治会主催の追悼会が開かれ、壇上に飾られた2人の肖像画は図書館に保管された。
法政から自由な校風を奪った
学内対立の「調停役」
だが伝統の自由な校風が消えるきっかけとなったのが、法政騒動だった。調停役として学内の実権を握った竹内は、今の岡山県倉敷市に生まれ、陸軍士官学校に入学するが、上官とけんかをして退官。日露戦争に従軍した後に法政大学で学び、司法試験に合格して弁護士になった。
そのかたわら、『法学志林』という法政大学法学部の機関誌に書いた「発明を論ず」という論文が、国粋主義的な司法官僚で後に首相に就任する同郷の平沼騏一郎に絶賛され、右派の人脈で縁を持った東京帝大の上杉慎吉に師事する。
上杉は、東京帝国大の国粋主義を唱える興国同志会を組織し、門下には、滝川事件などでリベラル派の言論人攻撃の先頭に立った蓑田胸喜がいた。竹内は会の結成に参加し、機関誌作りを担った。