25年間で1459本なので、計算上は1年に58本余りの報告書が提出されたことになる。「内調 委託事項」には複数の異なる筆跡が認められ、内調の内部で書き継がれてきたと考えられる。
ただし、志垣が事務局を務め、「志垣資料」に報告書が残っている核政策の委託などが入っておらず、すべてを網羅しているわけではないようだ。
ここでは試しに、納入月日が1969(昭和44)年のものを見てみよう。
志垣が学者担当の第5部主幹になってから2年目、東大の安田講堂事件、中ソが衝突した珍宝島(ソ連名・ダマンスキー島)事件、沖縄の「72年返還」決定など、国内外で大きなニュースが相次いだ年である。
この年に納入された委託レポートは、「委託外」、「講演」を含め70件。「委託外」は、内調の職員が学者から聴き取るなどしたものと見られる。そのうち、グループへの委託は9件で、重要な内容が目に付く。
北方領土問題や公明党・創価学会も
それぞれ3本取り上げられた
題名からテーマを類推すると、多いのは「70年問題」12本、学生運動9本、中国7本、核・原子力6本など。翌年6月に「70年問題」を控えていたことや、前年の1968(昭和43)年からフランスの「五月革命」や日本の全共闘運動など世界中でスチューデントパワーが巻き起こったことを反映した結果だろう。
他に、北方領土問題、公明党・創価学会がそれぞれ3本取り上げられていることも興味深い。
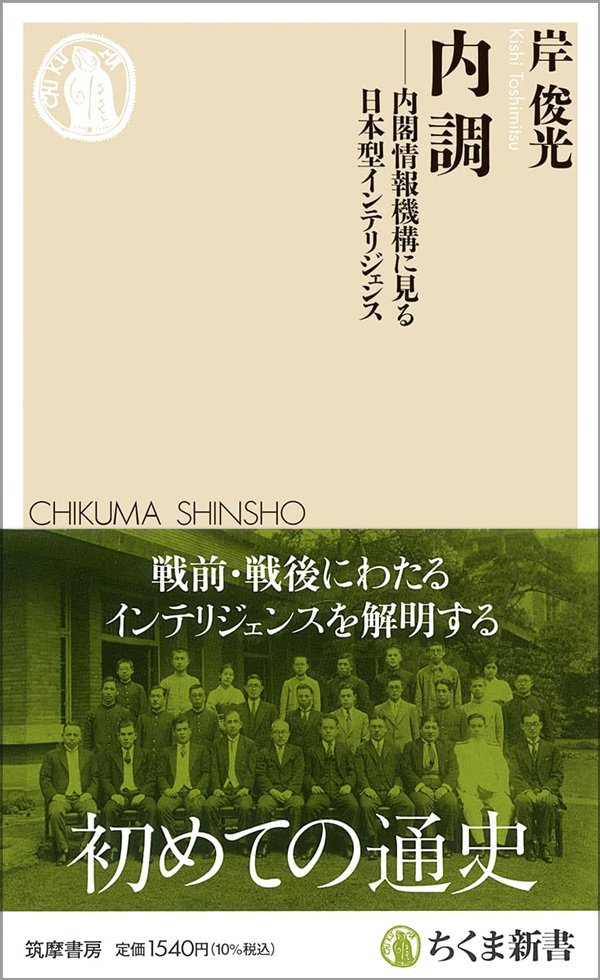 『内調――内閣情報機構に見る日本型インテリジェンス』(岸 俊光、筑摩書房)
『内調――内閣情報機構に見る日本型インテリジェンス』(岸 俊光、筑摩書房)
注目すべきは、執筆者に石川忠雄(慶應義塾長、中国現代史)、相場均(心理学、早稲田大学教授)、藤原弘達(政治学者、評論家)、吉村正(自民党中央政治大学院長、政治学)、本間長世(東京大学教授、アメリカ政治)、高坂正尭(京都大学教授、国際政治学)、見田宗介(東京大学教授、社会学)、神谷不二(慶應義塾大学教授、国際政治学)、佐伯喜一(野村総合研究所社長、防衛庁防衛研修所所長)ら有力な学者、実務家が名を連ねていることである。
現実主義の学者を中心に人脈が拡大して、旺盛に活動していた様子がうかがえる。国会図書館が収集・保存する資料を検索したところ、民主主義研究会が委託団体になった報告書が200件ヒットした。これらを精査すれば、個別の委託研究をある程度評価できるかもしれない。







