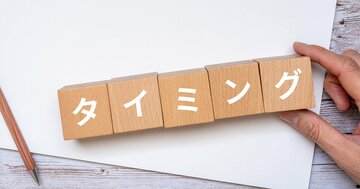チャンらの研究では、「積極的な先延ばし」をする人は、先延ばしてはいるものの、彼らの自信の高さや抑うつ、学校の成績などが、先延ばしをしていない人とほぼ同程度であることが示されています。
先延ばしをしやすい人の特徴には、課題に対する自信が低かったり、課題へのプレッシャーを感じやすかったり、抑うつが高かったりという傾向がありました。しかし、「積極的な先延ばし」をする人の特徴には、課題を先延ばし、締め切りが迫るなどのプレッシャーがかかった状態でこそ、自らのパフォーマンスを発揮できる、いわば「土壇場の強さ」があげられています。迫ってきたタスクに対し、プレッシャーのかかった状態で自身の能力をフル稼働させ、結果的に締め切りまでにタスクを完了させるのです。
土壇場になってからタスクにとりかかっても時間内に終わらせるためには、「自分ならこのタスクをこのくらいの時間でできる」という自信や確信が不可欠です。「積極的な先延ばし」をする人は、こうした見通しをもって、与えられたタスクと時間をうまくマネジメントできているともいえます。
ギリギリまで動かないのは
期限内に終える自信がある証拠!?
「あえての先延ばし」が功を奏するかの分岐点はまさしく、この見通しにあるといえるでしょう。「『あえて先延ばし』てるの!」と堂々といえるときは、きっとどこかで「今やらなくても絶対に終わらせられる」という確固たる自信があるのだと思います。その結果、タスクを時間通りに完了させることができます。
しかし、どこかで見通しが曖昧だったり、土壇場でとりかかったら間に合わないかも、本当にできるかわからない、と考えたりしているときは、「あえて先延ばし」た結果が、単なるセルフコントロールの失敗に終わってしまいます。
「とりあえず今はやらない。たぶん間に合う、大丈夫」とか、「モチベーションがあがってきたらやる」とあえて先延ばした結果、締め切りに遅れてしまうことは、まさしく根拠のない自信による落とし穴です。
「締め切り間近まで追い込まれないととりかかれない」という人も、与えられているタスクと自らが土壇場に発揮するパフォーマンスの関係がはっきりとイメージできていれば「積極的な先延ばし」となりますが、そうでない場合は「単なる先延ばし」になってしまいます。