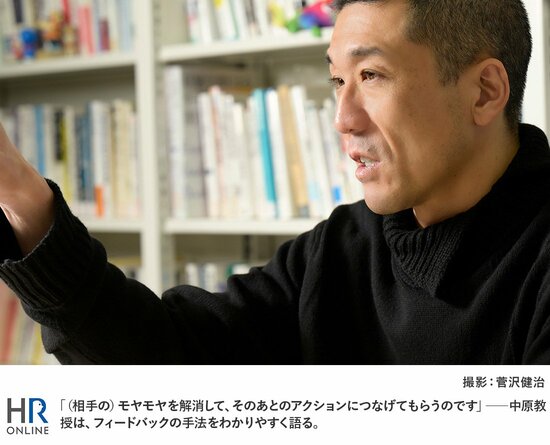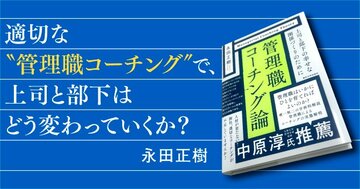「情報通知」と「立て直し」というふたつの要素
若手社員の離職を防ぎ、部下の成長を促進するためには、適切なフィードバックを行う必要がある。フィードバックには、さまざまな定義や手法があるが、中原教授は、「情報通知」と「立て直し」のふたつの要素からフィードバックは成立するとしている。
中原 フィードバックをするときに必要なものとして、「SBI情報」があります。これは「シチュエーション(Situation)」「ビヘイビア(Behavior)」「インパクト(Impact)」の頭文字で、どういう状況のときにどのような行動をとったことが、どういうインパクトや影響をもたらしたか、を意味します。これらを具体的に伝えて、「どう思う?」と相手にボールを投げること――それが、「情報通知」です。「狭義でのフィードバック」は、そこまで、です。しかし、ボールを投げられたままだと言われた側にはモヤモヤ感が残ります。ネガティブな情報通知はもちろんのこと、たとえ、ポジティブなことを言われたとしても、「どうして褒められたのだろう?」と考えてしまうかもしれません。通知して終わりではなく、次の目標に向けて一緒に考え、支援してあげること――これを、私は「立て直し」と呼び、広義のフィードバックとして定義しました。モヤモヤを解消して、そのあとのアクションにつなげてもらうのです。フィードバックにおいては、この「立て直し」という行為がとても重要になります。
「立て直し」がことさら大切な理由――それは、フィードバックを受ける部下とフィードバックを行う上司や管理職の仕事の成果に強くつながるからだと中原教授は言葉を続ける。
中原 そもそも、マネジメントとは、「他者を通じて成果を出すこと」です。マネジャーがやるべきことは、その一言に尽きます。フィードバックも、成果を出すための手段です。たとえ、“刺さる”フィードバックをしたとしても、成果が出なかったら意味がありません。成果を出す方向に向けて、相手のモヤモヤを解き放ってあげることが必要なのです。
「情報通知」だけなら、AIでもできますが、大切なのは、本人がその気になって、「次から、自分の考え方や行動を変えていこう!」と思うようになることです。エモーショナルな部分に働きかけるのは、人間でないとできません。フィードバックにおける「立て直し」こそが、上司やマネジャーの仕事と言ってもいいでしょう。