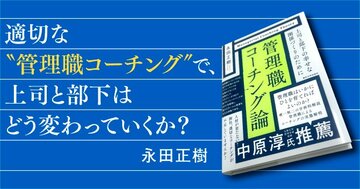いつの頃からか、「フィードバック」という言葉が日常的に使われるようになった。「フィードバック」は、相手の行動や成果を「評価すること」「指摘すること」などと把握されているが、その価値や適切な方法はあまり知られていないのではないだろうか。仕事における「フィードバック」とは、いったいどのようなものか? どう行えば、人材を育成し、当人の成長に結びつけることができるのか? 組織における人材育成・リーダーシップ開発についての研究を続け、書籍『フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術』の著者でもある中原淳教授(立教大学経営学部)に話を聞いた。(ダイヤモンド社 人材開発編集部、撮影/菅沢健治)
「フィードバック」という言葉は浸透しているが…
人材・組織開発の視点から、中原教授は、仕事における「フィードバック」は、とても重要な行動であり、部下育成の方法として欠かせないものだと明言する。
中原 「フィードバック」とは、「相手がどういう状態にあり、どういう行動をとっているのか?」という情報を“成長の鏡”のように、相手に返してあげることです。「自分にいちばん遠いところにいるのが自分」という言葉がありますが、自分のことは自分自身では意外にわかりません。また、本当に正しい行動をしているのかどうかも自分では判断しづらい。他者にどのように見えているのかを他者から教えてもらう必要があります。
そうしたフィードバックを得て、フィードバックを受けた当人は、これからどうしていくのがよいかを考えます。それが、経験学習サイクルにおける「振り返り(内省)」にあたります。つまり、フィードバックは、経験学習を回すための手段でもあるのです。
中原教授は、書籍『フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術』の執筆に至った理由として、「企業の現場において、フィードバックのニーズが非常に高まっていること」「『年上の部下』に代表される、職場の多様な人材に悩まされるマネジャーが増えてきていること」「ハラスメントに対する意識が職場で過剰に高まったこと」「言うべきことをしっかり言うという文化がおざなりになってしまったこと」「目標管理制度の運用を見直すところが増えてきていること」の5つを挙げている(*)。
出版から約8年の月日が経った現在でも、そうした状況はあまり変わらず、適切なフィードバックは、組織にとって喫緊の課題になっている。
* 書籍『フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術』(PHP研究所)より
中原 いまから10年ほど前、海外では、フィードバックは人材育成のための手法として最も研究され、かつ、効果が高いものとして認識されていました。一方、当時の日本では、言葉自体があまり行きわたっていませんでした。上司と部下のやりとりが「フィードバック」ではなく、ただの「ダメ出し」のようになってしまっていて、「このままではいけない」と思い、私は筆を執りました。HR領域において、当時から変わったことといえば、「フィードバック」という言葉が浸透したくらいでしょうか。一方で、昨今の学生は「先生、フィードバックをください」と、日常的に言ってきます。自分のやっていることの方向が合っているのか、外側から見てどうなのか、という情報を欲しがる傾向にあります。そのような若い世代が、入社後に適切なフィードバックを得られなければ、自分の成長を感じることはできず、早期離職につながる可能性も出てきます。

中原淳 Jun NAKAHARA
立教大学 経営学部教授
東京大学教育学部卒。立教大学大学院経営学研究科リーダーシップ開発コース主査、立教大学経営学部リーダーシップ研究所副所長などを兼任。「大人の学びを科学する」をテーマに、企業・組織における人材開発・組織開発についての研究を行っている。『企業内人材育成入門』『研修開発入門』『組織開発の探究』(すべてダイヤモンド社)、『職場学習論』『経営学習論』(東京大学出版会)、『フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術』(PHP研究所)など、著書多数。