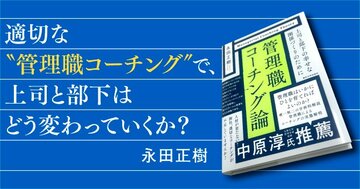「人は、簡単には変わらない」ということが前提
授業やゼミを通して、日々、学生にフィードバックを行っている中原教授。その、中原教授自身の姿勢にも、適切なフィードバックのヒントがありそうだ。
中原 私は、基本的に、相手が受け取れるものしかフィードバックしません。学部生だったらこれくらいだけど、大学院生だったらもう少しいけるだろうと、相手の伸び代に合わせてフィードバックをするようにしています。
ゼミでフィードバックをしたときに、学生から何も言葉が返ってこないことがあります。その場合、私は、「いま、みんなは沈黙しているけど、心の中で何を感じている?」と尋ねます。そうすると、学生それぞれで違う答えが返ってきたり、同じことを考えていたり……いろいろな本音が出てきます。そこで、私は出てきた言葉をそのまま使い、「いま、○○○○と言ったけれど」と、次の発言を促します。自分で発した言葉は否定できないので、相手の言葉を“呼び水”として次の言葉を呼び寄せるのです。
他に、私が気をつけているのは、「〜するな」「〜すべき」という言葉を使わないこと。それは相手が決めることであって、私の仕事は決めることのお手伝いです。時々、学生から、「先生が決めてください」と言われることもありますが、自分のことは自分で決めるのが肝心です。
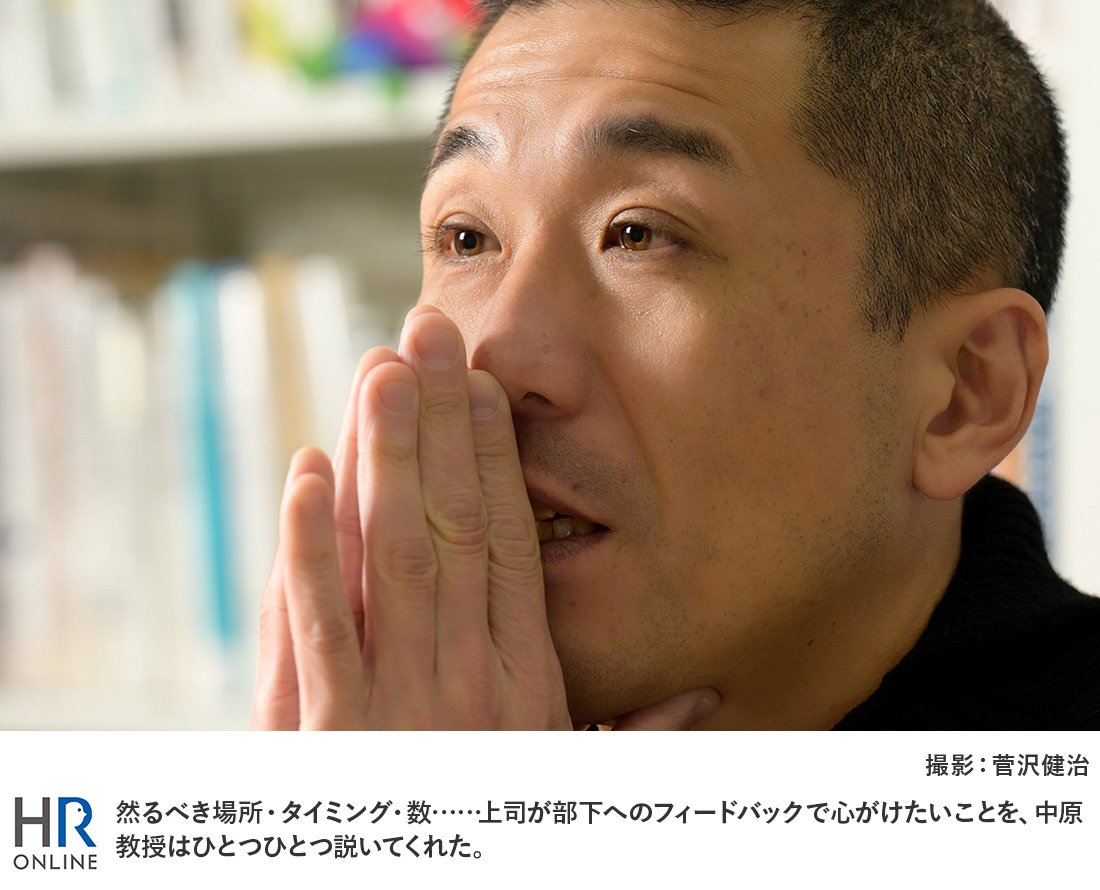
ポイントを押さえながらフィードバックをしたとしても、相手によってはうまくいかないケースもあるだろう。中原教授は、それも「当たり前」と語る。
中原 「人は、簡単には変わらない」ということが前提です。フィードバックをする側は、継続していくしかありません。私は、自分の仕事は「ツボ押し」だと思っています。押しても効かない場合が多いけど、たまに効くと、相手がヒュッと伸びる。「ツボ押し」は、一発で成功するものではないと割り切ったほうがいいですね。効かなければ、言い方を変えてみるのもひとつの手です。子どもに、「どうして、字をきれいに書かないの?」と言い続けても変わらないのに、「きれいに書いたほうがかっこいいよ」と言えば、変わることもありますから。