狩野南
オンラインセミナーでわかった、“アンコンシャスバイアス”に気づく意味
「外国人の従業員は日本語が苦手にちがいない」「育休中の女性は出張での仕事を嫌がるだろう」「シニア社員はITには詳しくないはず」――そんな“思い込み”が、職場での会話に散見する。あらゆる属性の人がさまざまな働き方をする昨今、アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)を減らすことは、ダイバーシティ&インクルージョンを目指す企業・組織にとって欠かせない姿勢だ。今秋、多くの企業関係者が参加したオンラインセミナー「組織・チームを蝕むアンコンシャスバイアスの対処法」を、「HRオンライン」がリアルタイムで視聴した。

立教大学・中原淳教授が語る、“フィードバック”の価値と、その適切な方法
いつの頃からか、「フィードバック」という言葉が日常的に使われるようになった。「フィードバック」は、相手の行動や成果を「評価すること」「指摘すること」などと把握されているが、その価値や適切な方法はあまり知られていないのではないだろうか。仕事における「フィードバック」とは、いったいどのようなものか? どう行えば、人材を育成し、当人の成長に結びつけることができるのか? 組織における人材育成・リーダーシップ開発についての研究を続け、書籍『フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術』の著者でもある中原淳教授(立教大学経営学部)に話を聞いた。

「アンコンシャスバイアス」のセルフラーニング動画を見て、私が気づいたこと
「あの人は育児中だから地方出張は嫌がるだろう」「外国籍の彼は日本人のマナーを理解しづらいにちがいない」――そんな思い込みで、対人関係にフィルターをかけてしまうことが職場で見受けられる。「無意識の偏見や思い込み」を「アンコンシャスバイアス」と呼び、企業・団体においては、「アンコンシャスバイアス」を研修によって理解し、減らしていく動きを進めている。そもそも、「アンコンシャスバイアス」とは何か? 働きやすい職場をつくるために心がけたいことは? 「アンコンシャスバイアス」のセルフラーニング動画から学んでみよう。
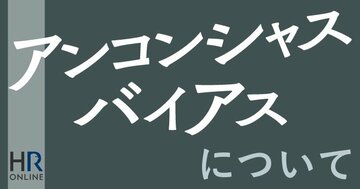
会社の“カルチャー”や新制度を、社員が意識し、仕事に反映させるために
多くの企業が、ミッション・ビジョン・バリューや経営理念を掲げているが、社員への浸透に腐心している経営層も少なくない。スポーツ競技におけるチームは、「勝利」という目標をメンバーが常に意識することで強くなる。そして、共通する思いがチームの雰囲気をつくり、チーム特有の“カルチャー”を醸し出していく。企業内の組織も同じだ。そうしたなか、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念で、多種多様なウエディング情報サービス事業を行っている株式会社ウエディングパークは、社員が醸し出す“カルチャー”が事業推進の源泉になり、ワークエンゲージメントを高めている。執行役員であり、コーポレートデザイン本部・本部長の戸田朱美さんに話を聞いた。

【ミュージカル研修(後編)】若手社員は、変化し続ける組織の中で、変化し続けられる人であってほしい
自動車に関する複合的なサービス(カーライフのトータルサポート)を行うプレミアグループは、2007年の創業からわずか10年で東証二部に上場(翌2018年12月に東証一部へ市場変更、現在はプライム市場へ移行)し、躍進を続けている。同グループのエンジンとなっているのが「人」だ。2020年には、グループ役職員を対象とした研修を企画・実施する会社として、株式会社VALUEを設立。「常に前向きに、一生懸命プロセスを積み上げることのできる、心豊かな人財を育成します」というMISSIONを掲げ、“人財”を輩出している。そのユニークな研修のひとつ“バリューミュージカル研修”は、なぜ、どのようにつくられたのか?

【ミュージカル研修(前編)】入社3年目社員が、チームで物語を創り、歌って踊って、気づいたことは何か?
自動車に関する複合的なサービス(カーライフのトータルサポート)を行うプレミアグループは、2007年の創業からわずか10年で東証二部に上場(翌2018年12月に東証一部へ市場変更、現在はプライム市場へ移行)し、躍進を続けている。同グループのエンジンとなっているのが「人」だ。2020年には、グループ役職員を対象とした研修を企画・実施する会社として、株式会社VALUEを設立。「常に前向きに、一生懸命プロセスを積み上げることのできる、心豊かな人財を育成します」というMISSIONを掲げて、“人財”を輩出している。そのユニークな研修のひとつ“バリューミュージカル研修”を「HRオンライン」がレポートする。

人事パーソンのリアルな悩みが表れた、『シン・人事の大研究』読書会
書籍『シン・人事の大研究 人事パーソンの学びとキャリアを科学する』が多くのHR関係者に読まれ、読者レビューでも好評だ。当書籍は、人事部門で働くビジネスパーソンたちの仕事・学び・キャリアを調査するプロジェクト『シン・人事の大研究』をまとめたもので、令和時代の人事パーソンの悩みや考え方がわかり、課題解決の気づきを読者にもたらしてくれる。そして、著者3人をゲストに招いた読書会にはさまざまな企業の人事担当者が集い、“人事仕事の現在”を共有した。「HRオンライン」が、その様子をつぶさにレポートする。

人材育成としての「内定者フォロー」が、内定辞退と早期離職を減らしていく
来春(2025年4月)に企業に入社する「25卒生」は、ストレートで大学に進学し、学部生としての4年間で卒業予定であれば、高校3年時に、“夏の甲子園”が唯一なかった学年(2002年4月生まれ~2003年3月生まれ)だ。つまり、新型コロナウイルスの影響を大学受験時にまともに受けた世代である。そんな彼・彼女たちが企業から入社の内定を受け、あと半年あまりで社会に飛び立とうとしている。自分たちが置かれる環境の変化に敏感な彼・彼女たちに対して、受け入れ側の企業は、いま、この時期に、どのようなフォローを行えばよいか。「内定者フォロー」のセミナーを開催し、さまざまな企業の人事担当者と接点を持つ有識者(御明宏章さん)に、「HRオンライン」が話を聞いた。
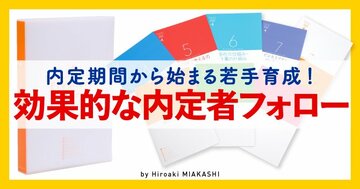
企業は、いまどきの新入社員たちにどう向き合い、何をしていけばよいか
24卒の新入社員が各企業に入社して約半年が過ぎた。人事部では、25卒の内定者フォローに切り替えている採用・教育担当者が多いだろう。そうしたなか、キャリア志向のある、昨今の新入社員は、職場の不満を口にしないまま、入社1年も経たないうちに離職してしまうケースがある。企業の人事部は新入社員にどう向き合うべきか――「『フレッシャーズ・コース(FC)』を活用した自律型新入社員研修」のプログラム設計を手がけるほか、新入社員の入社後フォロー研修の講師としても活躍する内山厳さんに話を聞いた。

ビジネスで、日常で、相手を受け入れる、“牛窪流”「聞く」「話す」メソッドとは?
世代間コミュニケーションの難しさを感じているビジネスパーソンに読まれている良書がある。書名は、『なぜか好かれる人の「言葉」と「表現」の選び方』『難しい相手もなぜか本音を話し始めるたった2つの法則 入門・油田掘メソッド』――著者は、どちらも、元NHKキャスターの牛窪万里子さんだ。25卒内定者向けメディア「フレッシャーズ・コース2025」にも出演している牛窪さんは、これまでに5000人以上をインタビューしてきた「聞く」「話す」ことのスペシャリストであり、フリーアナウンサーが所属する企業の経営者でもある。「HRオンライン」が、そんな牛窪さん自身の発する言葉に耳を傾けた。

研修で学んだことをどうすれば仕事に活かせるか――“研修転移”の実践方法
2018年6月に発売された書籍『研修開発入門 「研修転移」の理論と実践』が、ウィズコロナの時代に、人事(研修)担当者のバイブルになっている。企業の経営・人事側からすれば、時間と労力をかけて行った研修での学びを、受講者には日々の仕事で少しでも役立ててほしいはず。しかし、実際は、研修を「やりっぱなし」で終わるケースも多いだろう。書籍の共著者であり、昨年(2023年)9月に「“研修の転移と評価”実践会」を立ち上げた、株式会社ラーンウェル 代表取締役の関根雅泰さんに話を聞いた。

この4月に入社2年目を迎えた新入社員は、“フォロー研修”で何を得たか?
コロナ禍での就職活動を経て、昨年2023年4月に企業・団体に就職した新入社員――「『フレッシャーズ・コース2023』を活用した自律型新入社員研修」の一環として、入社3カ月後と入社6カ月後に行われた“新入社員フォロー研修”の総決算として、今年2月に、“最後のフォロー研修”が行われた。「経験学習」を繰り返しながら、自分の「強み」や「良さ」を仕事にどう生かしていけばよいか――これまで同様に、研修会場を訪れた「HRオンライン」が、その学びの様子をレポートする。

“ビリギャル”小林さやかさん「キャリアづくりに必要なのは、ワクワクしたら飛び込む力」
「ビリギャル」刊行から10年。主人公のモデル小林さやかさんは、現在、米国コロンビア大学教育大学院で研究生活を送っている。高校生の時に偏差値30台から慶應義塾大学に現役合格を果たした彼女は、卒業後ウエディングプランナーとして働き、30代で海外に留学。次のキャリアを描こうとしている。その節目節目で「決断する力」の源泉となったものは何だったのか。

入社から6カ月時点の “23卒新入社員の成長”を研修から読み取る
コロナ禍で就職活動を行い、昨年2023年4月にさまざまな企業・団体に就職した新入社員たち――「『フレッシャーズ・コース2023』を活用した自律型新入社員研修」の一環として、入社3カ月後に行われた“新入社員フォロー研修”に続き、昨秋、都内某所で、入社6カ月後の研修が実施された。彼ら彼女らは、それぞれの職場でどう働き、何を学んでいるのか。そして、今回の研修で自分たちの仕事をどう表現したのか――前回同様に、研修会場を訪れた「HRオンライン」が、その様子を詳細にレポートする。
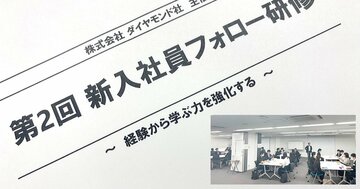
人も職場も社会も変わる“ダイバーシティコミュニケーション”とは何か?
“多様性”“ダイバーシティ”という言葉が人口に膾炙(かいしゃ)し、「人的資本経営」というキーワードも重要視されている現在(いま)、企業経営層や管理職、人事担当者は、「ダイバーシティ&インクルージョン」や従業員の「キャリア自律」にどう向き合えばよいのだろう。「個人が自分のキャリアを自分事としてとらえ、変化を恐れずに、自分を磨きつづける。組織は多様性と向き合い、一人一人の価値を最大限に引き出す経営を目指す」――株式会社キャリアンサンブル代表の垂水菊美さんはそう語る。「ダイバーシティ」について、「キャリア」について、そして、垂水さんが提唱する「ダイバーシティコミュニケーション」について、話を聞いた。

立教大学・中原淳教授の書籍が、“オンライン読書会”の参加者に伝えたこと
今年(2023年)6月に刊行された書籍『人材開発・組織開発コンサルティング 人と組織の「課題解決」入門』(立教大学経営学部教授 中原淳 著/ダイヤモンド社刊)が、企業の経営層や人事担当者に広く読まれている。A5判・464ぺージの大著だが、多くの図版とともに展開されるページは、読みやすく、とても丁寧なつくりで、誰もが理解できる内容だ。その「オンライン読書会」が、参加費無料で、9月の2夜にわたって行われた。各回200名以上の参加者でにぎわったイベントの様子を「HRオンライン」がレポートする。

23卒の新入社員が入社後3カ月の“フォロー研修”で学んだことは…
マスクを着けた人も減り、昨年2022年とは社会の景色がすっかり変わった2023年の夏――4月に入社した新入社員たちも、それぞれの職場や仕事に慣れつつあった。そうした複数の企業のフレッシャーズを対象に、入社3カ月後(2023年7月時点)の“新入社員フォロー研修”が行われると聞き、「HRオンライン」は都内の研修会場を訪ねた。“配属後の自分自身の変化を振り返る”というワークから始まった研修、はたして、その内容は……。
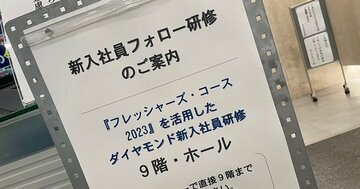
“ナナメウエ”のアウトプットが、組織と個人のこれからを成長させていく
「“ナナメウエの”ユニークな仕掛けのある場」を提供し、「一人ひとりの、個性ある“ナナメウエの”面白いアウトプット」を促進し、「組織・個人・ビジネスの“ナナメウエの”成長」をもたらすことを生業にしている研修講師がいる。八住敦之さん(ピラミッド計画・代表)――ヴィレッジヴァンガードの店舗でのマネジメント経験やイベント、ワークショップなどの場づくりの経験を生かし、オリジナルな発想とプログラムで「アイデア創発」や「リフレクション」研修などを行い、企業の注目を集めている。八住さんがメッセージする“ナナメウエ”とは何か? 「HRオンライン」が話を聞いた。

いまどきの新卒社員がオンラインでの“新入社員研修”で学んだこと
ウィズコロナの時代が新たなステージを迎えるなか、4月からスタートした2023年度も第1Qの終盤を迎えている。4月入社の新卒社員はそれぞれの職場に配属されて、仕事を覚えている毎日だろう。今年4月、「HRオンライン」は、オンラインで行われた、2日間にわたる新入社員研修(『フレッシャーズ・コース2023』を活用した自律型新入社員研修)を取材した。Z世代の新入社員たちは、オンラインで、何をどう学び、それぞれの職場に戻ったのか? その研修内容を詳細にレポートする。
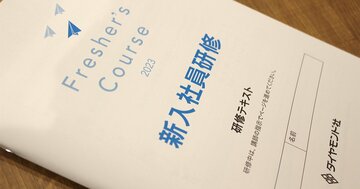
人的資本、オンライン、内製化……「研修」はこれからどうあるべきか?
コロナ禍によって、企業における「研修」はオンラインの受講が一般化し、研修動画のオンデマンド視聴なども増えている。また、コロナ禍前から研修の「内製化」が進む一方で、人的資本経営やダイバーシティ&インクルージョンの推進によって、研修の内容も多岐にわたっている。ウィズコロナ、アフターコロナの時代で、企業内の研修はどうなっていくのか。部下育成研修などで講師を務めるほか、さまざまな経営者や人事部と接点を持つ永田正樹さんに、「研修」の現況とこれからの意義を「HRオンライン」で語ってもらった。
