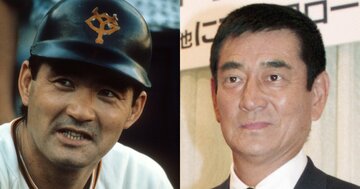「海外にある軍隊は現地に於いて復員し、内地に帰還せしむることに努むるも、止むを得ざれば、当分その若干を現地に残留せしむることに同意す。(中略)賠償として一部の労力を提供することには同意す」
特使派遣は、既に対日参戦を決めていたソ連の同意を得られず、実現しなかった。だが「賠償としての労力提供」案が日本側の一部で検討されていた事実は否定できない。
では密約はあったのか。ジャリコーワでの「停戦交渉」のほぼ唯一の生き証人、瀬島龍三は『大本営の回顧』に当時の模様をこう記している。
「会見室に入った。ガランとした10畳位の室だ。まん中に、粗末なテーブルがある。向う側に元帥ばかり5人並んでいた。ほかには通訳らしい少佐が1人だけ、あとはだれもいなかった」
双方の簡単なあいさつの後、関東軍総参謀長、秦彦三郎と瀬島が机の手前側に座った。向かいの中央が極東ソ連軍総司令官ワシレフスキー。その左右に方面軍司令官マリノフスキーら4人が並んだ。5人とも50歳以下の若いつやつやした顔色の元帥だ。胸に勲章が所狭しと飾られていた。
瀬島が語った「停戦交渉」には
大きなウソがあった
会談は約3時間続いた。瀬島によると、秦が最も強く要求したのは(1)在満州居留民の早期日本帰還(2)関東軍将兵の居留民に次ぐ帰還(3)ソ連軍などの暴行の取り締まり――つまり瀬島は「交渉」でシベリア抑留が話し合われた事実はなく、逆に関東軍側は将兵の早期帰還をソ連側に強く要求したと言う。だが……。
ワシレフスキーの副官だった元共産党国際部副部長イワン・コワレンコが語る。
「瀬島は事実と違うことを言っている。関東軍将兵の帰還を要望したなんてうそだ。そもそもあの会談は(対等な立場の)停戦交渉じゃない。勝者が敗者に命令を下す場だったんだ。秦は関東軍の降伏状況報告のため連れて来られ、ワシレフスキーからほぼ一方的に指示を受けただけだ」
当時、関東軍への政治宣伝に携わっていたコワレンコは会談に同席した副官らから会談内容の報告を受けていた。