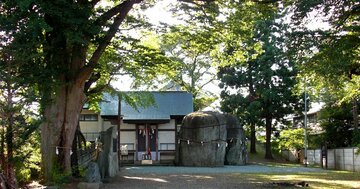崩落のリスクを懸念してか、柵で保護され、壕の中に立ち入ることはできないが、柵越しに内部を覗き見るだけでも、往時のムードを思わせる物々しさが感じ取れるはずだ。
 陸軍用地を示す境界石。かつての駒沢練兵場の痕跡だ
陸軍用地を示す境界石。かつての駒沢練兵場の痕跡だ
 当時の人々は、どのような思いで豪の中にいたのだろうか
当時の人々は、どのような思いで豪の中にいたのだろうか
「お台場」の由来にもなった
外国船の侵入を防ぐ軍備
ターゲットを幕末にまで広げてみれば、注目すべき遺構はさらに増える。たとえば、品川区に遺された浜川砲台跡である。京急線・立会川駅からほど近くにある新浜川公園に見られるもので、日本沿岸に外国船がたびたび姿を見せるようになった江戸時代末期、外国船対策の一環で随所に砲台が設置された。
立会川には「浜川」という別称があり、当時はこちらの呼称が主流であったことから浜川砲台と呼ばれ、現在は大砲のレプリカが存在感を発揮している。
 浜側砲台跡地に設置されたレプリカ
浜側砲台跡地に設置されたレプリカ
ちなみにこのエリアには全部で8つの砲台が置かれていたそうで、他所では丸太を大砲のように見せた偽物も多く見られたことから、浜川砲台は江戸っ子にとって誇らしい軍備であったという。
臨海の人気エリア・お台場にしても、もとは江戸幕府が外国船の侵入を防ぐために築いた砲台の台場に由来することはよく知られている。戦争遺跡は都市開発と共に消滅する運命にあり、都内ではどうしても数が限られてしまうが、視点ひとつで戦時中のさまざまな痕跡が見つけられるはずだ。
戦後80年のいま、あらためてそうした遺構のいくつかに目を留めることが、学びや気づきのきっかけになることを願って止まない。