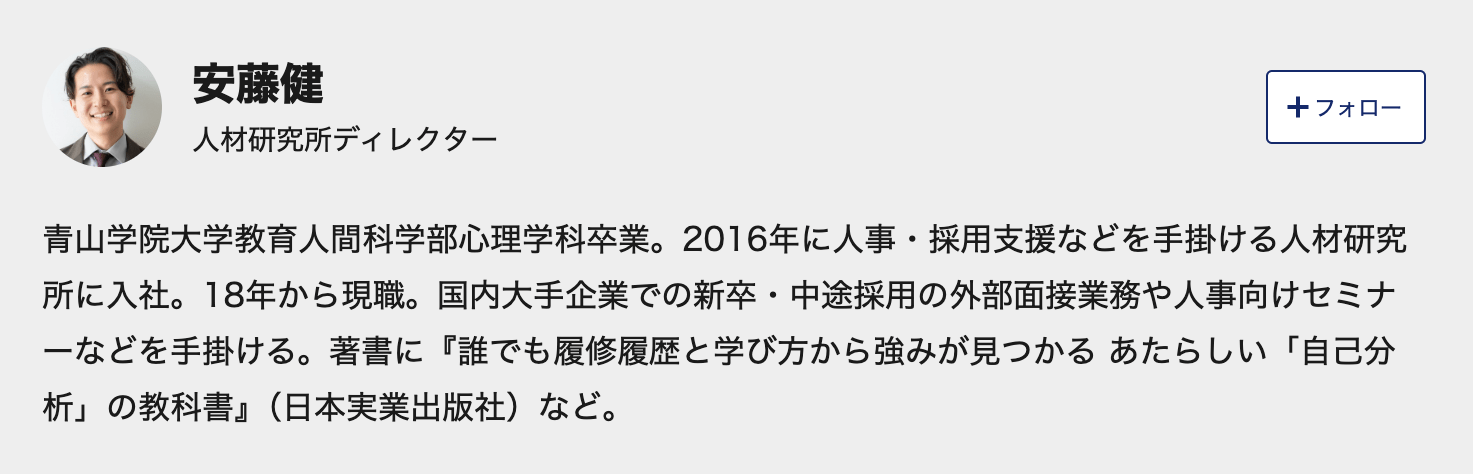上司として何ができる?
やりがい搾取と思われない目標の伝え方
とはいえ、上司が部下に対して、やりがい搾取と受け取られないように目標を伝えるのは非常に難しいものです。その人の将来を本当に考えて、心からサポートしようという気持ちでやっているか。本人にとって耳の痛いことであっても、教育的観点から今言わないと将来的にまずいことをきちんと伝えられるか。
こうしたことはマネージャーになるための必須要件と言えるでしょう。それができなければその場限りの口当たりのいいことを言うだけの上司になってしまいます。
上司が意識すべき重要な理論として、カナダの心理学者ヴィクター・ブルームが提唱した「期待理論」※3があります。モチベーションは「期待」と「誘意性」の掛け算で決まるというものです。
期待とは、その行動をすることで、どのくらいの報酬が得られるか。誘意性はその報酬がその人にとってどれくらい魅力的かを指します。
例えば、新規のプロジェクトを部下に任せる際、「この仕事をやれば、こんな報酬(お金以外に、成長やキャリアの発展、昇進可能性も含みます)が得られる」と説明するだけでは不十分です。上司が、部下にとって魅力的であろうと考えたからといって、部下にとっても同じように魅力的とは限らないため、誘意性――その報酬が当人にとってどれだけ魅力的か――も意識して、意味づけを考える必要があります。
この意味で、上司が部下に行き当たりばったりの会話で仕事を依頼するのは一番良くないやり方です。
「あなたがこの仕事をするのは、あなたにとってもよいことだと思う」と提案するためのロジックや戦略をしっかり持ったうえで面談をしなければなりません。そうした準備がなければ、部下に「この人は本当に私のために言っているのだろうか」と不信感を持たれてしまいます。
といっても、相手を言いくるめる、とか、「決め打ち」で進めるということではありません。部下としても「こうやりたい」「こうありたい」という思いがあるはずで、上司の思いと部下の思いの2つがあって、初めて対話が成立します。
具体的には、なぜその部下にこの仕事をアサインしたいのか、それは当人にどんな意味があるのか、そもそも当人は、何にやる気を感じているのかなどを予め整理しておきます。仕事を任されれば部下はモチベーションが上がるかもしれないが、こういう不安も抱えるだろうということも予想し、会社はそれをどうサポートできるかも含めて考えておきます。
これは、心理カウンセリングと同じです。カウンセリングはその内容の100%が会話で成り立ってはいますが、カウンセラーは面談前にクライエント(患者)についてあれこれ思いを巡らせ、面談で何を持ち帰ってもらおうか入念に準備をしています。そうした準備があってこそ、面談後に、このセッションを受けて良かったと思ってもらえるのです。
こうした「真剣勝負」や「直接対決」の場面で、アドリブができる人はそうそういません。部下のことを深く考える時間を事前に取っていてこそ、やりがい搾取ではない、真に部下のためになる意味づけを行うことができます。それをするのが本来の上司の役目なのです。
荷が重いと思われるでしょうか。しかし、部下が納得し、やりがいを持って仕事に取り組み、成長する姿を見られることは、それこそ上司冥利に尽きるというものだと思います。