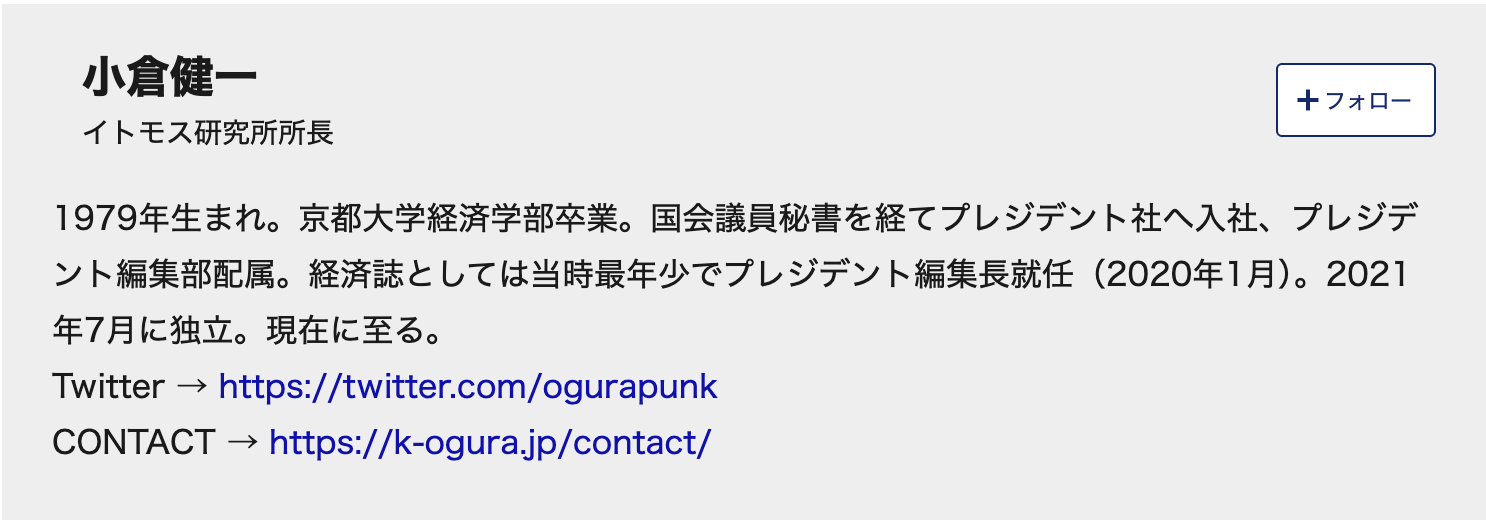適応できない人は切り捨てられる!?長期的に考えると組織に悪影響も
「Sink or Swim」という思想は、企業を成長させる原動力になった一方で、冷たい側面もある。挑戦を促す力が成果を生んだ半面、適応できない人を切り捨てる仕組みにもなっていた。
『ユニクロ帝国の光と影』には「泳げないものは溺れればいい」という言葉が社内の緊張感を保つために使われたと記されている。この言葉は社員を鼓舞するメッセージであると同時に、適応できない人を排除する論理でもあった。
短期的には業績を高める効果があるかもしれないが、現代の経営では持続可能性や心理的安全性といった価値観が重視されている。心理的安全性とは、組織の中で安心して意見や感情を表せる状態を指す。
過度に「Sink or Swim」を強調すると、失敗を恐れる文化が広がり、心理的安全性が大きく損なわれる。社員は常に淘汰の恐怖にさらされ、精神的に疲れ果ててしまう。
その結果、創造的なアイデアや率直な議論が失われ、組織全体の力が長期的に落ちてしまう危険がある。
挑戦を続ける姿勢は企業にとって不可欠である。だがそれを支える教育の仕組みや、失敗から学ぶことを許す環境づくりも欠かせない。個人の努力だけに頼るのではなく、組織が「泳ぎ方」を教え、必要なときには支える体制を持たなければ、持続的な成長は望めない。
結局「泳げない者は沈めばいい」という言葉は、柳井氏やゲイツ氏が経営に臨む覚悟を表した強いメッセージだったということだろう。
現代のビジネスパーソンには、この言葉の厳しさを踏まえつつ、柔軟さや包み込む姿勢をどう取り入れるかが問われている。適者生存という原則は変わらないかもしれないが、何を「適応」と呼ぶかは時代とともに変化している。
生き残るのが本当に大変な時代に突入した。