まず、彼らの生活や1日の流れを想像する。どんなメディアに触れ、どのタイミングで情報を得ているのかを考える。そして、そのなかのどこで「3つのランプ」を点灯させることができるかを探るのだ。
朝起きてスマホでXやYahoo!ニュースを確認し、友人からのLINEをチェックする。駅から電車に乗り、移動中にスマホでYouTubeを視聴。テレビ局に到着して勤務先のチャンネルの情報番組をチェックしたあと、1日の仕事をこなす。退勤後、再び電車に乗りニュースやYouTubeを視聴し、帰宅。家ではスマホで動画を楽しみ、最後に友人からのLINEを確認して1日を終える。
こうしてリストアップできるのが、「ウェブ記事」「Yahoo!ニュース」「LINE NEWS」「YouTube番組」「情報番組」「電車広告」などの具体的な接点だ。このなかからアプローチの難易度が低いものを選び、重点的に取り組むことで効果的な施策が見えてくる。
このなかで、比較的取り組みやすいのがウェブ記事の活用だ。多くの出版社は自社のウェブメディアを持っている。
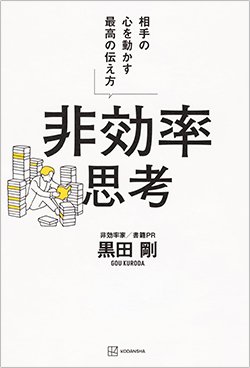 『非効率思考 相手の心を動かす最高の伝え方』(黒田 剛、講談社)
『非効率思考 相手の心を動かす最高の伝え方』(黒田 剛、講談社)
また、さまざまなウェブメディアには、本の内容を紹介できる抜粋記事やインタビューの掲載枠がある。まずはウェブ記事を積極的に発信することで、「3つのランプ」を点灯させることができる。
ウェブ記事が注目を集めれば、その後、情報番組での紹介へとつながる。さらに、ランプが次々に点灯し、電車広告やYouTube番組へと展開しながら、メディアでの紹介が次々と広がっていく。
このようにアプローチを細分化し、次に取るべき行動を明確にすることで、効果的に進めることが可能だ。
メディアの人たちの「ランプ」が点灯していくにつれて、企画会議で著者や本の認知度が高まり、提案が通りやすくなる。
そう考えると、どんなに小さなメディアにも手間を惜しまずアプローチしておくことが結局、後々の成果につながっていくのだ。







