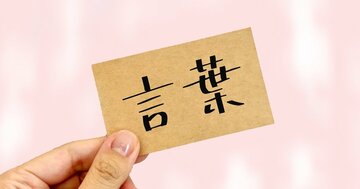少しでも共有できるものがあるだけで、不思議と安心感が芽生え、そのつながりが会話の種となって、自然と人間関係が広がっていくのです。
共通点はつくり出すものだと教えられ、今も強く心に刻まれているのは、大広時代に出会った建設省(現国土交通省)の官僚、竹村公太郎さんの言葉です。
「教養ってなんだか知ってるか?」
当時、河川局長だった竹村さんにこう問いかけられ、私は答えに詰まりました。
そんな私に、竹村さんは「どんな人とも馬を合わせて会話ができることだよ」と教えてくれたのです。
知らない話題が出た時は
どうすればいい?
馬を並べて歩かせるように、相手の歩調に合わせる。それを可能にするのが、教養だというわけです。竹村さんが教えてくれたのは、ただのうなずき上手ではなく、相手が切り出してきたどんな話題にもついていける力を身につけること。
教養とは単なる知識ではない、相手との共通点を見つける引き出しなのだと、目が覚めるようだったことを思い出します。
そう考えれば、教養を身につける手段は、学校や書籍で学ぶばかりではありません。漫画、映画、音楽、スポーツ、釣りに手芸に料理、それから世界のニュースを知ることも、あらゆることが教養に結びつきます。
私は、新聞の切り抜きをスクラップすることを習慣としていました。新聞に目を通すと、自分の関心分野以外の情報についても知ることができる。新しい興味を持つきっかけにもなる。ネット配信のニュースにはない、新聞のよさだと感じています。
サイバーエージェント社長の藤田晋さんも、毎朝、新聞を読むらしく、「世の中の動きを知るために、自分の興味のないジャンルが目に入ってくることが大事」と言っていました。
もちろん、すべての話題に精通している必要はありません。しかし、相手の話に対して、「それについては不勉強なのですが、ぜひ教えてください」と素直に関心を寄せることもまた、大切な聞く力であり、教養のある人の姿です。
会話とは知識の披露ではなく、関係を築くためのもの。