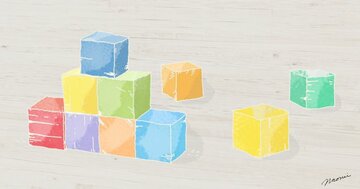「思い込み」が、障がい者雇用の問題を引き起こす
障がい者雇用については、私自身も“実践中の当事者”である。神戸大学の障がい者雇用を刷新し、軌道に乗せる仕事に深く関わっている。神戸大学は、清掃活動を職務とする知的障がい者を多く雇用しているのだが、雇用している障がい者が良い働きをするための条件において、たくさんの課題がある。法定雇用率が年々上がってきている今日、新たな障がい者雇用システムの創出が必要な状況にある。
その仕事の関連で、私は先日、神戸大学の内々の幹部セミナーで講演を行った。学長をはじめとする神戸大学の経営陣に障がい者雇用への意識を喚起する稀有な機会だったため、障がい者雇用もやり方によっては神戸大学の価値を高める取り組みになり得るのだ、ということに力点を置いて話をした。苦しくなる一方の国立大学の財政事情、また、イノベーションをもたらす研究成果を求められる圧力が強まる状況のなか、神戸大学の障がい者雇用は「義務としてやっておかなければならない取り組み」に過ぎないとされる傾向があり、優先順位が下がりがちである。しかし、だからこそ、神戸大学の幹部には、「障がい者に任せられる仕事は少ない」という「思い込み」を取り除いて、「やりようによっては新しい価値を生み出すかもしれない挑戦なのだ」という気持ちになってもらいたいと思った。
大学でも企業でも、組織の構成員が「障がい者は仕事ができない」「障がい者雇用は自分の職務とは接点がない」といった「思い込み」が支配していることは多い。その「思い込み」が、障がい者雇用の問題を引き起こす。雇用された多くの障がい者が、組織の構成員から切り離され、低賃金で周辺的な仕事を与えられる。また、最初から期待されずに雇用されている障がい者は、経営状況が悪化すると真っ先に解雇される。「障がい者には価値のある仕事ができない」といった経営陣の「思い込み」を取り除くことは、障がい者雇用を進めていくうえで、真っ先に取り組まなければならないことのひとつなのだ。
「思い込み」とは、思い込んでいることにさえ気づかない考えをいう。したがって、「思い込み」に気づくことは、たやすいことではない。「思い込み」が障がい者雇用を進めるうえでのハードルになっているとしたら、そのハードルをどのように下げることができるだろうか。一年履修コースで障がい者雇用について研究を進めている社会人学生の話を聞きながら、「思い込み」について考えることにした。