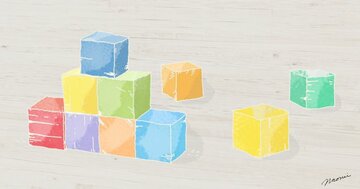「思い込み」のハードルを下げるために仕掛けたこと
一年履修コースで修士論文執筆に取り組んでいる今井進吾さんは、現在、歯科クリニック(医療法人社団わく歯科医院)の管理本部本部長としてクリニックの経営を担っている。このクリニックは、院長の強い信念のもとで、人を大切にする精神が根づいている。昨年(2024年)、第14回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞の厚生労働大臣賞を受賞しており、その授賞理由には「過去10年間で、離職者が1人ということからもわかるように、人財教育・福利厚生制度など、ハード・ソフトの両面から社員を大切にする経営が行われている」とある。
今井さんがこのクリニックで最も力を入れているのが障がい者雇用である。現在は、聴覚障がい者1名、知的障がい者1名が、クリニックの他の従業員と良好な関係を築き、仕事に打ち込んでいるが、この状態になるまでの道のりは平坦ではなかったという。
最初に院長が障がい者雇用に挑戦することを切り出したとき、クリニックの現場から懸念の声が上がった。医療ミスが許されない医療現場では、安全と衛生が最優先される。現場のスタッフたちは、障がい者にこの規律を守ってもらうことができるのだろうかという不安があったのだという。そこで、院長の思いに共感した今井さんが、この医療法人で管理本部本部長となり、現場のスタッフの理解を得ながら、障がい者雇用を進める役割を担うことになった。
今井さんはまず、従業員一人ひとりと面談して、「なぜ、障がい者雇用が必要なのか?」ということについて話し合いを仕掛けた。案の定、多くの従業員から、安全と衛生の観点から障がい者雇用に対する後ろ向きな発言があった。しかし、じっくりと話を聞いていくなかで、それぞれの背景や思いがあることも分かっていった。なかには、身内に障がい者がいることを語ってくれたスタッフもいた。今井さんは、スタッフの思いに共感しながら、障がい者が社会的な活動を制限されている状況を一緒に変えていこうと訴えかけた。
そのうえで今井さんは、毎月1回、障がい者雇用で実績のある人を講師に招いて、幹部を対象にした勉強会を開いた。質疑応答の時間をたっぷり設けたところ、幹部たちから、「実際に障がい者に仕事ができるのか?」「効率が悪くなるのではないか?」といった質問が講師にぶつけられた。講師は、「歯医者さんは、お金儲けのために始めたのですか? 患者さんの歯を治療するために始めたのでしょう? 同じように儲けるためではなく、一緒に働くために障がい者を雇用するのです」と答えた。このやりとりを境に、幹部たちの間に「いままでの考え方が間違っていたのかも」という雰囲気が広がっていった。
加えて、今井さんは、2回目の勉強会から、勉強会後の食事会を企画し、幹部以外のスタッフにも声をかけた。食事会に参加したスタッフたちは、本音で自分の考えを語り出し、講師とも、歯に衣着せない対話をし始めた。こうした取り組みの結果、しばらくすると、クリニックの現場スタッフのなかから、「近所にも障がい者がいました」「障がい者雇用は考えるまでもなく始めるべきです」といった声が出るようになっていった。
4回目の勉強会を開いた頃に、ハローワークから聴覚障がいのある福田さん(仮名)の照会があった。スタッフの気持ちも障がい者雇用に前向きになりかけていたところだったため、福田さんにクリニックで働いてもらうことにした。
福田さんは、働くために必要なことを自分自身で周囲に伝えることのできる人だった。スタッフたちも福田さんの要求や希望に耳を傾けることで、徐々に福田さんにとって働きやすい職場環境が生まれていった。そうしてまもなく、消毒滅菌作業を福田さん一人でもミスなくこなすようになった。福田さんは、クリニック全体で楽しむ懇親会にも参加し、他の従業員との関係も深まっている。現在では、自発的に手話講座に通い始めたスタッフも複数人いる。
「思い込み」のハードルを下げるために今井さんが仕掛けたのは、本質的なテーマに即して本音で対話ができる場づくりだった。そして、その「本音」のなかに、「思い込み」に気づくきっかけが潜んでいたのだ。