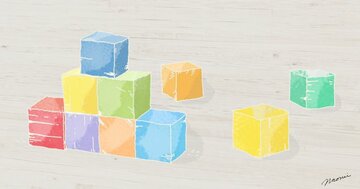学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第19回をお届けする。
* 連載第1回 「生きづらさを抱える“やさしい若者”に、企業はどう向き合えばよいか」
* 連載第2回 ある社会人学生の“自由な学び”から、私が気づいたいくつかのこと
* 連載第3回 アントレプレナーの誇りと不安――なぜ、彼女はフリーランスになったのか
* 連載第4回 学校や企業内の「橋渡し」役が、これからのダイバーシティ社会を推進する
* 連載第5回 いまとこれから、大学と企業ができる“インクルージョン”は何か?
* 連載第6回 コロナ禍での韓国スタディツアーで、学生と教員の私が気づいたこと
* 連載第7回 孤独と向き合って自分を知った大学生と、これからの社会のありかた
* 連載第8回 ダイバーシティ&インクルージョンに必要な「エンパワメント」と「当事者性」
* 連載第9回 “コミュニケーションと相互理解の壁”を乗り越えて、組織が発展するために
* 連載第10回「あたりまえ」が「あたりまえではない」時代の、学生と大学と企業の姿勢
* 連載第11回「自由時間の充実」が仕事への活力を生み、個人と企業を成長させていく
* 連載第12回 “自律”と“能動”――いま、大学の教育と、企業の人材育成で必要なこと
* 連載第13回 特別支援学校の校長を務めた私が考える、“教え方と働き方”の理想像
* 連載第14回「いかに生きるか」という問いと、思いを語り合える職場がキャリアをつくる
* 連載第15回 なぜ、学生たちは“ボランティア”をするのか?――その背景を知っておくことが大切
* 連載第16回 手軽になった動画ツールや情報は、私たちの学びにどのような影響を与えるか
* 連載第17回 韓国の大手企業が知的障がい者の劇団と取り組んだ研修――その目的とは?
* 連載第18回 大学から力強く巣立っていく外国人留学生が、企業で活躍するために…
リカレント教育における、障がい者雇用への関心
大学は、産業界との連携をますます求められるようになってきている。その一環として、政府はリカレント教育の推進に力を入れている。企業人が大学で学び直しの機会を得ることは、個々人の人生を豊かにするという意味でも、また、企業の力を向上させるという意味でも、有意義である。
私の勤める神戸大学大学院人間発達環境学研究科は、高度職業人養成プログラムを創設して20年になる。一年間で修士号を得ることのできる一年履修コースである。さまざまな組織で実績のある社会人が、職業経験のなかで生まれてきた問いをもって入学し、密度の高い学びの成果として、修士論文を仕上げる。
私も、その一年履修コースを担当する教員の一人として、毎年、さまざまな関心と背景をもつ社会人と出会ってきた。最近の傾向として感じるのは、「障がい者雇用への関心から学び直しを志す社会人学生が増えている」ということだ。その背景には、「誰一人取り残さない社会」が目指されるなか、労働市場から排除されてきた障がい者の働く権利を保障しようとする機運の高まりがあるのだろう。障がい者雇用促進法に則って、障がい者を雇用する企業のすそ野は広がりつつある。それとともに、雇用した障がい者が企業価値を高める働きをするためには、どのような環境や支援が必要であるかという問いも広く共有されるようになってきていると感じる。
学生たちは修士論文のために多くの先行事例を調査したり、先行研究を読んだりする。そうした学びの過程を経て、障がいのある従業員を大切に扱う組織風土や、企業理念、経営者層の考え方に焦点を当てるようになっていく。障がい者雇用が成功するかどうかは、障がいについての知識や支援のノウハウはもとより、より根本的な企業のあり方、経営のあり方について見直すことが肝心なのだと考えるようになっていくからなのだと思う。